| < 怪奇城の外濠 Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
怪奇城の外壕 Ⅲ
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ix. もろもろ(2)
いろいろなど(2); ガストン・バシュラール、『空間の詩学』、1972 バシュラールについて→こちらを参照:「通史、事典など」の頁の「vi. 四大その他」 オットー・フリードリッヒ・ボルノウ、『人間と空間』、1978 B.ルドルフスキー、渡辺武信訳、『建築家なしの建築』(SD選書)、鹿島出版会、1984 原著は Bernard Rudolfsky, Architecture without Architects, 1964 序/ムユ-ユレイ(Muyu-uray)の円形劇場/死者の家/オルデクの死者の都/パンタリカ(Pantalica)の穴居人の街/穴居生活/住居は下に、田畑は上に/建築家としての自然/引き算による建築/引き算による建築(続き)/敷地の選択/高巣の建築/イタリアの丘陵都市/モデル的な丘陵都市/ドゴンの断崖居住者/水の都市/遊牧民の建築/原始的な形態/建築的擬態/都市の構造/単位的建築/古典的風土性/要塞化した場所/家族的規模の要塞建築/スバネティアの要塞化村落/アーケード/アーケード(続き)/アーケード(続き)/覆われた通り/半ば覆われた街路/ロジア(Loggie)/準・聖堂型建築/穀物倉(続き)/小規模の穀倉/貯蔵用の塔/貯蔵用の要塞/肥料熱成装置/技師のいない機械技術/杭上住居/骨格建築/ハイデバラード・シンドの空調設備/天界の建築/象徴的風土性/無装飾の城砦/草の構造体/民芸的建築における木材/囲い/牧歌的建築/編まれた王宮/可動建築/草木の屋根/原始的な 180ページ。 B.ルドルフスキー、平良敬一・岡野一宇訳、『人間のための街路』、鹿島出版会、1973 原著は Bernard Rudolfsky, Streets for People, 1969 序章/破壊による発展/豚のための街路/街路の推薦状/キャノピーのある街路/逍遙学派/路上のドラマ/街路の個性/階段を讃えて/橋と高架街路/続・キャノピーのある街路/迷路/ダイヤモンドの街路と水晶の舗道/青い噴水/カフェと街路/犯罪の報復/展望など、 344ページ。 バーナード・ルドルフスキー、渡辺武信訳、『驚異の工匠たち 知られざる建築の博物誌』、鹿島出版会、1981 原著は Bernard Rudolfsky, The Prodigious Builders, 1977 脱線しがちの序論/図版についての覚え書/洞窟を讃えて/野性の建築/建築が遊戯であった時代/移動する建築/穀物と死者の倉/城塞/消えゆく風土性/正当に評価されていない風土建築/ささやかな部分の重要性/ミノタウロスの呼び声/不法占拠への讃歌/積木欲望/「建築家なしの建築」についての覚え書など、 436ページ。 荒俣宏、『ヨーロッパ・ホラー紀行ガイド』、講談社、1996 地下牢の恐怖 シヨン・スイス/青ひげ城の幼児虐殺 チフォージュ・フランス/怪物ゴーレム伝説 プラハ・チェコ/郵便夫の「霊廟」 オートリーブ・フランス/魂を吹きこむ人形師 ヌシャテル・スイス/パラゴーニアのお化け屋敷 パゲーリア・イタリア/謎の町レンヌ レンヌ・ル・シャトー・フランス/巨石が示すレイライン カルナック・フランス/「狂王」の脳内遊園地 ミュンヘン・ドイツ/生きている死少女 タルクィニア・イタリア/うめく「蠟人形」 フィレンツェ・イタリア/天国と地獄に通じる庭園 ジェノバ・イタリア/自分のための死の部屋 ロリオル=シュル=ドローム・フランス/パリの地下の巨大迷宮 パリ・フランス/吸血鬼ドラキュラ トランシルバニア・ルーマニア/ロンドンの幽霊ツアー ロンドン・イギリスなど、 278ページ。 同じ著者による→こちらも参照:「魔術、神秘学、隠秘学など」の頁の冒頭あたり 古市徹雄、『風・光・水・地・神のデザイン - 世界の風土に叡知を求めて』、彰国社、2004 まえがき 歴史が創り上げたまち、建築を訪ねて/風 - 知恵と工夫/光 - 空間のドラマ/水 - 自然が創り出す都市/地 - 大地に描かれた都市/神 - 絶対的支配など、 250ページ。 写真集; 尾形一郎、尾形優、『HOUSE』、有限会社フォイル、2009 ナミビア:室内の砂丘/中国:洋楼/ギリシャ:鳩小屋/沖縄:構成主義/メキシコ:ウルトラバロック/日本:サムライバロックなど ミシェル・フーコー、佐藤嘉幸訳、『ユートピア的身体/ヘテロトピア』(叢書 言語の政治 20)、水声社、2013 原著は Michel Foucault, Le corps utopique, Les hétérotopies, 2009 (1966年12月7日、21日のラジオ講演より) ユートピア的身体/ヘテロトピア// フーコーと身体的書き込みのパラドックス(ジュディス・バトラー、1989)/「ヘテロトピア」 - ヴェネチア、ベルリン、ロサンゼルス間のある概念の苦難(ダニエル・ドゥフェール)// フーコー的ユートピア/ヘテロトピアから抵抗へ - 解説にかえて(佐藤嘉幸)// 訳者あとがきなど、 148ページ。 山本陽子、「コラム 怪異が現れる場所としての軒・屋根・天井」、東アジア恠異学会編、『怪異を媒介するもの』(アジア遊学 187)、勉誠出版、2015、pp.94-99 身近な怪異の場所/軒端の魔除け/さかさまの幽霊/屋根や軒から出現する理由/軒や屋根に現れる怪異/失われる異空間 →こちらでも挙げました:「怪奇城の高い所(前篇) - 屋根裏など」の頁 他の内容は; はじめに(大江篤)// 記す・伝える;霊験寺院の造仏伝承 -怪異・霊験譚の伝播・伝承(同)/『風土記』と『儀式帳』 - 恠異と神話の媒介者たち(榎村寛之)/コラム 境界を越えるもの - 『出 雲風土記』の鬼と神(久禮旦雄)/奈良時代・仏典注釈と霊異 -善珠『本願薬師経鈔』と「起屍鬼」(山口敦史)/コラム 古文辞学から見る「怪」 -荻生徂徠『訳文筌蹄』『論語徴』などから(木場貴 俊)/「妖怪名彙」ができるまで(化野燐)// 語る・あらわす;メディアとしての能と怪異(久留島元)/江戸の知識人と〈怪異〉への態度 - 〝幽冥の談〟を軸に(今井秀和)/クダンと見世物(笹方政紀)/コラム 霊を捉える - 心霊学と近代の作家たち(一柳廣孝)/「静坐」する柳田国男(村上紀夫)// 読み解く・鎮める;遣唐使の慰霊(山田雄司)/安倍吉平が送った「七十二星鎮」(水口幹記)/コラム 戸隠御師と白澤(熊澤美弓)/天変を読み解く - 天保十四年白気出現一件(杉岳志)/コラム 陰陽頭土御門晴親と「怪異」(梅田千尋)/吉備の陰陽師 上原大夫(木下浩)// 辿る・比べる;王充『論衡』の世界観を読む - 災異と怪異、鬼神をめぐって(佐々木聡)/中国の仏教者と予言・讖詩 - 仏教流入期から南北朝時代まで(佐野誠子)/中国の怪夢と占夢(清水洋子)/中国中世における陰陽家の第一人者 - 蕭吉の学と術(余欣)/台湾道教の異常死者救済儀礼(山田明広)/コラム 琉球の占術文献と占者(山里純一)/コラム 韓国の歴書の暦注(全勇勲)/アラブ地域における夢の伝承(近藤久美子)/コラム 〈驚異〉を媒介する旅人(山中由里子)など、 294ページ。 菅谷優、「屋上ヘテロトピー 社会空間への眼差し」、『武蔵野美術大学研究紀要』、第51号、2021.3.1、pp.53-59 [ < 武蔵野美術大学機関リポジトリ ] 廣田龍平、「ノスタルジック・ホラー バックルームとコアの世界」、『早稲田文学』、vol.1036、2021秋、pp.70-78 バックルームという異空間/コアという美学/ノスタルジアの二つの恐怖 沖田瑞穂、『怖い家 伝承、怪談、ホラーの中の家の神話学』、原書房、2022 はじめに// 序章 怪異が出現する家;外からはいってくる ー 玄関と勝手口/住みついている/怖いイエ/ロシアの家の怪異・ドモヴォイとキキーモラ/「見るなの禁」と境界/天井裏/境界としてのトイレ/物語の転換点としての家/家と一体化している/乗っ取られる/閉じ込める/拡散する家の怪異// 異界の家 - 母胎と富;境界に建つ家/富をもたらす異界の家/なぜ竜宮城には富があるのか/小さ子が異界の富を現世に運ぶ/母胎としての異界の富/庭はあの世// 生まれなおす家 - 娘から女へ、少年から英雄へ;ハウルの城/ソフィーにおける少女と母/「ヘンゼルとグレーテル」と魔女のお菓子の家/赤ずきんのおばあさんの家/産み、そして命を回収する女/生みなおす女神、生まれなおす家/白雪姫のこびとの家/こびとの家に滞在する意味/鬼の家のイニシエーション① - サルデーニャ民話/鬼の家のイニシエーション② - 昔話「鬼が笑う」/試練の家、帰る家/(コラム)試練の家// 呑みこむ家;死の家/家と一体化する/家が呼ぶ/巣づくりに呑まれる女たち/有機的な家/家に吸い取られる// 閉じこめられる - 閉鎖空間としての家;怪物を閉じこめておく/女性が閉じこめられる/シーターの監禁/閉鎖空間によって加速する悪意・狂気/失われていく自立心// 「イエ」の継続と断絶;イエに向けられたお岩の呪い/血糖を途絶えさせる女・メディア/王家の継続に執着する男 - 『天空の城ラピュタ』/呪われた家系 - メリュジーヌ三姉妹と母プレシーヌ/呪いの家系 - 実在の呪力/家系の存続が絶対の義務 - インドの神話から/『マハーバーラタ』における王家の血統の存続/ソーマカ王の一人息子/手塚治虫『奇子』におけるイエと近親相姦の意味/(コラム)憑き物筋 イエに憑く動物/ギリシア神話の呪われた家系 - アガメムノンに至るまでの血筋// 終章 家は生きている// あとがきなど、 232ページ。 →こちらでも触れました:「怪奇城の高い所(前篇) - 屋根裏など」の頁 同じ著者による→そちらを参照:「インド」の頁の「ii. インドの神話とその周辺」 エマヌエーレ・コッチャ、松葉類訳、『家の哲学 家空間と幸福』、勁草書房、2024 原著は Emanuele Coccia, Filosofia della casa : lo spazio domestico e la felicità, 2021 邦訳は Emanuele Coccia, Philosophie de la maison : L'espace domestique et le bonheur, 2021 より(p.181) 序論 都市の彼方の家/引っ越し/愛/浴室とトイレ/家のなかの物/キャビネット/双子/白い粉/ソーシャル・ネットワーク/部屋と廊下/ペット/庭と森/台所/結論 新しい家、あるいは賢者の石// 謝辞/本書の成り立ち/参考文献// 訳者あとがきなど、 198ページ。
Joshua Comaroff + Ong Ker-Shing, Horror in Architecture. The Reanimated Edition, University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 2013 / 2023 『建築における 新版への前書き// 序/分身たちとクローンたち/優美な屍骸/部分的かつ大部分死んでいる/反復と反射/抑えきれない諸物体/トロイの馬/ホムンクルス主義と巨人主義/固いこと、塊、規矩術/歪曲と不均衡/不定形/人形たち/叛乱を起こした自然/置換/後記など、 272ページ。 →こちら(「オペラ座断面図」(1875)の頁の「Cf. の cf.」)や、そちら(シャルル・ド・ヴァィイ《コメディー・フランセーズの新たなホールの内部》(1771)の頁の「Cf.」)、またあちら(『巨人ゴーレム』(1920)の頁の「Cf.」)で挙げました 次の2冊はこのページの趣旨からすると真っ先に挙げるべきなのかもしれませんが、最初のものを読んだ時かなり難渋しました。当初は邦訳のせいかとも思ったのですが、2冊目でこちらがうまく同調できないことに思い至った次第です; アンソニー・ヴィドラー、大島哲蔵・道家洋訳、『不気味な建築』、鹿島出版会、1998 原著は Anthony Vidler, The Architectural Uncanny, 1992 はじめに/序// 住居;居心地の悪い家/生き埋め/ホームシック/ノスタルジア// 身体;寸断された建築/顔の喪失/トリック/トラック/地表面の変換/サイボーグのための家// 空間;闇の空間/ポストアーバニズム/サイコメトロポリス/夢幻性/放浪の建築/透明性など、 310ページ。 アンソニー・ヴィドラー、中村敏男訳、『歪んだ建築空間 現代文化と不安の表象』、青土社、2006 原著は Anthony Vidler, Warped Space. Art, Architecture, and anxiety in Modern Culture, 2000 まえがき/序文// 空間恐怖 パスカルからフロイトまでの虚空の構築/広場恐怖症 都市空間の精神病理/無限を枠に入れる ル・コルビュジェ、アイン・ランド、そして「えも言われぬ空間」/疎外の空間 疎外の建築:ジンメル、クラカウアー、ベンヤミン/行き止まりの街路 ヴァルター・ベンヤミンと気晴らしの空間/空間の爆発 建築と映画の虚像/メトロポリスのモンタージュ クラカウアー、ベンヤミン、エイゼンシュテインの映画としての都市/現場はここだ 犯罪現場の空間消失// ホーム・アローン ヴィト・アコンチの公共領域/フル・ハウス レイチェル・ホワイトリードの脱家事的キャスト/ロスト・イン・スペース トバ・ケドゥーリの建築的断片/ディープ・スペース/抑圧された記憶 マイク・ケリーの教育複合体/ターミナル・トランスファー マーサ・ロズラーのパッセージ/アンゲルス・ノヴス コープ・ヒンメルブラウの表現主義的ユートピア/バロックを越えて カルヴァー・シティのエリック・オーエン・モス/「デス・キューブK」 モーフォシスのネオフォーメーション/スキン・アンド・ボーンズ ライプニッツからリンまでの褶曲形態/エンプティ・スペースに建てる ダニエル・リベスキンドと脱空間の虚空/惑星、彗星、そしてダイノサウルス 前歴史的主体/脱歴史的アイデンティティーなど、 494ページ。 とても食欲をそそるタイトルなのに、やはり波長を合わせそこなったのが; マンフレッド・タフーリ、八束はじめ・石田壽一・鵜沢隆訳、『球と迷宮 ピラネージからアヴァンギャルドへ』、PARCO出版、1992 原著は Manfredo Tafuri, La sfera e il laberinto, 1980 序 歴史という計画=企画// 形象の黙示録;悪しき建築家 G.B.ピラネージ ヘテロトピアと旅/アヴァンギャルドの歴史 ピラネージとエイゼンシュテイン// アヴァンギャルドの冒険 キャバレーからメトロポリスまで;「虚像都市」としての冒険 フックスから全体劇場へ/ソヴィエト連邦 ベルリン 1922 ポピュリズムから「構成主義インターナショナル」へ/「社会主義都市」に向けて USSR 1917/ニュー・バビロン-黄色い巨人とアメリカニズムの神話 表現主義、ジャズ・スタイル、スカイ・スクレーパー、1913/ワイマール・ドイツにおける社会政策と都市// ガラス玉演技;閨房建築/ジェファーソンの遺灰など、 484ページ。 ……………………… 路地その他; 竹内裕二、『イタリアの路地と広場』(上下)、彰国社、2001 上 シチリアからプーリアまで はじめに// イタリアの路地と広場を考察する;地中海の住居地域/気持ちのよい路地/気持ちのよい広場// イタリアの路地と広場の形態;路地の原型 路地の形態を分析する - 10タイプの路地/広場の原型 広場の形態を分析する-10タイプの広場// イタリアの路地と広場;シチリア州/カラブリア州/バズィリカータ州/プーリア州など、 244ページ。 下 ロンバルディアからサルデーニャまで はじめに/ロンバルディア州/ヴェネト州/エミリア・ロマーニャ州/トスカーナ州/ウンブリア州/ラツィオ州/アブルッツォ州/カンパーニア州/サルデーニャ州など、 226ページ。 竹内裕二、『イタリア中世の山岳都市 造形デザインの宝庫』、彰国社、1991 イタリア中世の山岳都市とは;山岳都市の魅力 自然と歴史が息づく街/山岳都市の原型 中世・円形周壁都市の起源を探る// イタリア中世の山岳都市の住居形態;山岳都市の類似性 住居形態を分類する/山岳都市の建築図面 住居の10タイプ// イタリア中世の山岳都市;リグリア州/トスカーナ州/マルケ州/ウンブリア州/ラツィオ州/アブルッツォ州/プーリア州/シチリア州など、 260ページ。 同じ著者による→こちらを参照:「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「廊下など」の項 中里和人、『路地』、清流出版、2004 160ページ。 同じ写真家による→こちらを参照:本頁下掲の「綺想建築、その他」の項 『世界の路地裏 100』、ピエ・ブックス、2005 本文テキスト:加藤希 路地裏を歩く/コルドバ/家の壁が白く塗られているわけ/パリ/モンマルトル/ニース/ロドス島/エーゲ海の島々/ロバとの島の暮らし/リスボン/リスボンのケーブルカー/グアナファト/ブラーノ島/色とりどりの家/ヴェネツィア/ゴンドラの街/プラハ/プラハの街/ロンドン/ロンドンのパブ/里門洞 イムンドン/ソウルの下町など、 192ページ。 『日本の路地裏 100』、ピエ・ブックス、2005 監修・写真:佐藤秀明 日本の路地裏風景// 日本の路地裏案内;京都路地裏案内/祇園路地裏歳時記/金沢路地裏案内/路地裏が残る日本の街並/路地裏の街並に見られる日本の建築/東京路地裏案内/路地裏文学散策/路地裏が並ぶ日本の町々など、 192ページ。 島村昇・鈴鹿幸雄他、『京の町家 生活と空間の原理』(SD選書 59)、鹿島出版会、1971、pp.79-90:「ローヂ」 上田篤・田端修編、『路地研究 もうひとつの都市の広場』、鹿島出版会、2013 まえがき(上田篤)/ 序 路地とは何か ドヂの世界が今も?(上田篤)/ オールドデリーのチャンドニー・チョーク 群れ型に都市化する(中岡義介)/ジョグジャカルタのカンブン 安寧の路地(鳴海邦碩)/鹿港の巷 壊れやすい路地(角野幸博)/上海の里弄 方形街区の内部世界に迫る(高村雅彦)/北京の胡同 生活空間としての路地(金澤成保)/ソウルの北村韓屋村 美しさより居心地のよさ(久隆浩)/プラハのアールヌーヴォー・タウン 貧民の路地がアートの辻に(田中充子)/ベルリンのハケッシャホーへ 新しい住宅より古い家と中庭がいい(内山佳代子)/ニューヨークの路地空間 メガ・ヴィレッジの歩行者たち(渡辺真理)/京・大阪の都心路地空間 人工の都市から自然の都市へ(田端修)/ 結 対談 世界の路地・日本の路地 脱サラリーマン社会にむけて(陣内秀信+上田篤)/ あとがき(田端修)など、 320ページ。 ……………………… 住宅その他; S.カンタクシーノ、山下和正訳、『ヨーロッパの住宅建築』(SD選書 50)、鹿島出版会、1970 原著は Sherban Cantacuzino, European Domestic Architecture, 1969 起源;序論/メガロン型およびビット・ヒラニ型/ 城と宮殿/町屋/ 訳者解説など、 210ページ。 →こちら(「「廊下など、メモ」の頁)や、そちら(『ヘルハウス』(1973)の頁)、またあちら(「怪奇城の広間」の頁)でも挙げました 板倉元幸、『スペイン民家探訪』、ARTBOXインターナショナル、2004 ガリシア地方/アストゥーリアス、カンタブリア地方/バスク、ナバールラ、ラ・リオハ地方/カスティーリャ・イ・レオン地方/エストゥレマドゥーラ地方/アラゴン地方/カタルーニャ地方/バレンシア、ムルシア地方、バレアレス諸島、マドリッド、カスティーリャ・ラ・マンチャ地方/アンダルシーア地方など、 240ページ。 Bill Laws, photography; Joaquim Castells Benosa, Traditional houses of rural Spain, Abbeville Press Publishers, New York, London, Paris, 1995 『田舎のスペインの伝統的家屋』 ガリシア、アストゥーリアスとカンタブリア/アラゴーン、ラ・リオハ、ナバッラとバスク地方/カタルーニャ/カスティーリャ・イ・レオーン/カスティーリャ・ラ・マンチャとエストレマドゥーラ/アンダルシーアなど、 160ページ。 Joaquín de Yrizar, Las casas vascas. Torres/palacios/caseríos/chalets/mobiliario, Biblioteca Vascongada Villar, Bilbao, 1980 『バスクの家 塔、館、農家、山荘、家具』 序言/塔/館/都市部の民衆住宅/農家/現代建築/家具など、 144ページ。 マリー・ミックス・フォーレイ、八木幸二訳、『絵で見る住宅様式史』、鹿島出版会、1981 原著は Mary Mix Foley, The American House, 1980 序(ジェイムス・M・フィッチ)/はじめに// 中世の影響;イギリスの伝統/オランダの伝統/丸太の伝統と開拓者の家/ドイツの伝統/フランスの伝統/スペインの伝統// 古典時代;ジョージアン期/フェデラル期/グルークリバイバル// ヴィクトリア時代;ロマンチックなリバイバル様式/マンサードおよびスティックスタイル/サーフェス様式// アメリカンルネサンス;ボザールの館/伝統的様式// 近代住宅;アメリカの先駆者/国際建築様式/移行の場面など、 336ページ。 原題にあるとおりアメリカの住宅を扱ったもので、事典形式。 八木幸二・田中厚子、『アメリカ木造住宅の旅 建築探訪 3』、丸善、1992 東海岸の旅/西部の旅/南部への旅/カリフォルニアへ/さまざまな木造集合住宅など、 112ページ。 ウィンチェスター邸もちらっとではありますが、図版つきで言及されています(pp.78-79)。→こちらも参照:本頁中の「綺想建築など」の項 小倉暢之、『アフリカの住宅 建築探訪 6』、丸善、1992 ケニア ナイロビ-住宅の博物館/ケニア ラム島 - イスラム文化の島/黄金海岸 アクラ-50年代をリードした街/北部ナイジェリア ザリア、カノ-砂漠に近い街/住宅の周辺など、 112ページ。 木島安史、『カイロの邸宅 アラビアンナイトの世界 建築巡礼 11』、丸善、1990 アラビアンナイトの世界/カイロの邸宅/カイロの邸宅の特色など、 112ページ。 山本達也、『トルコの民家 建築探訪 8』、丸善、1991 トルコ的発想/トルコの都市/季節移住生活/民家の中のイスラム教/小宇宙としての部屋/連結の空間 - ソファー/平面の時代変遷/生活(日常-非日常)など、 112ページ。 森俊偉、『地中海のイスラム空間 アラブとベルベル集落への旅 建築探訪 14』、丸善、1992 イスラムの風景/マグリブのイスラム都市と集落/アラブイスラムの住まいと街/ベルベルイスラムの住まいと集落/人と生活/旅の風景など、 112ページ。 金光鉉、『韓国の住宅 土地に刻まれた住居 建築巡礼 20』、丸善、1991 まえがき - 韓国の住宅を見る二つの軸/自然・儒教・土地 - 土地と倫理の住居/集落と住宅の構成 - 両班の住居感覚/「マダン」の思考 - 外部の部屋/マルと内部空間 - 内部化された自然/表層と展開 - 透明な空間への広がりなど、 112ページ。 小松義夫、『地球生活記 世界ぐるりと家めぐり』、福音館書店、1999 アフリカ/ヨーロッパ/アジア/オセアニア/アメリカなど、 334ページ。 →『鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』(2005)+『鋼の錬金術師』(2017)の頁でも挙げました。 小松義夫、『カラー版 世界の不思議な家を訪ねて - 土の家、石の家、草木の家、水の家』(角川 one テーマ21)、角川書店、2006 土の家/石の家/草木の家/水の家など、 224ページ。 内田青蔵(文)・小野吉彦(写真)、『新装版 お屋敷拝見』(らんぷの本)、河出書房新社、2003/2017 はじめに// お屋敷の魅力とお屋敷めぐりの心得;お屋敷とは何か?/お屋敷の特徴/お屋敷の魅力/お屋敷の種類// お屋敷を見に行こう;ジョサイア・コンドル設計の住まい/宮家の住まい/旧大名家の住まい/時代を切り開いた人々の住まい// 近代日本住宅小史 - 洋館誕生事始/ 付 用語解説絵解き事典など、 144ページ。 旧山本有三邸(pp.102-105)に関し→こちら(『女吸血鬼』(1959)の頁)で、 また旧古河虎之助邸(pp.36-43)に関し→そちら(『血を吸う薔薇』(1974)の頁)で、 旧鳩山一郎邸こと鳩山会館(8pp.92-97、およびカヴァー表紙)に関し→あちら(「怪奇城の肖像(幕間)」の頁)で挙げました 増田彰久、『カラー版 西洋館を楽しむ』(ちくまプリマー新書 068)、筑摩書房、2007 序章 西洋館とは何か// 西洋館を用途別に楽しもう;灯台/税関/学校/役所/駅舎/工場/倉庫/レンガ窯/時計塔/教会/ホテル/邸宅/温室/刑務所// 〈コラム〉 西洋館を撮る①// 西洋館の細部を楽しもう;列柱/スレート/ベランダ/装飾金具/階段/食堂/暖炉/照明器具/ステンドグラス/タイル/漆喰装飾/植物装飾/動物装飾// 〈コラム〉 西洋館を撮る②// ぼくが選んだ西洋館ベスト10;富岡製糸場/中込学校/箱根富士屋ホテル本館/日本銀行本店/盛美館/自由学園 明日館/小菅刑務所/朝香宮邸/岩崎小彌太熱海別邸/日向別邸など、 192ページ。 黒崎敏、ビーチテラス編著、『可笑しな家 世界中の奇妙な家・ふしぎな家60軒』、二見書房、2008 142ページ。 中山繁信、『世界のスローハウス探検隊 日本・世界の「建築家なしの住宅」を巡る』、エクスナレッジ、2008 世界と日本にみるさまざまな住まい/住まい方の再考 目的・素材・場所など、 176ページ。 レオン・イザベ/ルブラン設計・製図、中島智章訳・監修、『VILLAS 西洋の邸宅 19世紀フランスの住居デザインと間取り』、マール社、2014 原著は Léon Isabey et Leblan, Villas. Maisons de ville et de campagne, 1867 監修のことば(中島智章)/様式別一覧/原書序文 ヴィラ 都市住宅と郊外住宅// 図版// 用語集/索引など、 128ページ。 全55の見開きを1単位に(その内 Plate 12, 27 は前の番号でとりあげた建物の別図)、縮尺つきでファサードの立面図、1階や2階などの平面図(屋根裏などはなし)と解説を掲載。 美術史に興味があれば「Plate 25:クールベ氏の郊外住宅兼アトリエ[オルナン]」(pp.62-63)、また「Plate 47:芸術家の住宅」(pp.106-107)なんてのが見逃せないかもしれません。 →こちら(「怪奇城の広間」の頁)や、そちら(「怪奇城の画廊(前篇)」)、またあちら(「怪奇城の高い所(前篇) - 屋根裏など」の頁)、こっち(「怪奇城の高い所(中篇) - 三階以上など」の頁)でも挙げました イーフー・トゥアン、阿部一訳、『個人空間の誕生 食卓・家屋・劇場・世界』、せりか書房、1993 原著は Yi-Fu Tuan, Segmented Worlds and Self : Group Life and Individual Consciousness, 1982 全体;分節化・意識・自己/結合体// 部分;飲食とマナー/家屋と家庭/劇場と社会/環境と視覚// 自己;自己/自己と再構成された全体など、 310ページ。 →こちら(「秘められた欲望の花園を求めて」の頁)、またそちら(「怪奇城の広間」の頁)でも挙げました 原口秀昭、『20世紀の住宅 空間構成の比較分析』、鹿島出版会、1994 空間と空間構成 - 原口秀昭氏と20世紀の住宅(鈴木博之)// 西洋の独立住宅;3分割構成と中心性/英国の伝統とラッチェンスのカントリーハウス/アメリカの伝統とライトのプレーリーハウス/アヴァンギャルドたちの住宅/均質空間への道程 ミース・ファン・デル・ローエの独立住宅/反均質空間の勃興/解体と再生の歴史// 日本の独立住宅;日本の伝統と中廊下型平面/伝統的構成の変形 1900-1945/オープンプランの追求 1945-1960/60年代以降の独立住宅/開放と閉鎖の歴史// プロトタイプの空間構成の比較分析など、 198ページ。 →こちらで少し引きました:「廊下など、メモ」の頁 また 『愉しき家』展図録、愛知県美術館、2006 1st;愉しむ家(拝戸雅彦)/図版など、 88ページ。 2nd;会場図/図版/解説と作家によるテキストなど、 108ページ。 →こちらで少し触れています:「ユダヤ Ⅲ」の頁の「おまけ」 堀賀貴、「古代ギリシャ・ローマ都市住宅における上部空間に関する研究」、『日本建築学会計画系論文集』、59巻456号、1994.2、pp.247-253 [ < J-STAGE ] DOI: https://doi.org/10.3130/aija.59.247 金山弘昌、「『 DOI https://doi.org/10.24581/nihonbashi.6.0_29 ……………………… 客家民居; 岡田健太郎、『客家円楼 中国・福建省・広東省・江西省』(旅行人ウルトラガイド)、旅行人、2000 旅の技術/客家と客家建築/福建省 閩西地区/福建省 閩南地区/広東省 粤東地区/広東省 粤北地区/江西省 贛南地区など、 128ページ。 茂木計一郎、片山和俊、写真:木寺安彦、『客家民居の世界 孫文、鄧小平のルーツここにあり』、風土社、2008 序言/はじめに(片山和俊)/客家のすがた(木寺安彦)// 客家の由来[客家住居覚え書](茂木計一郎)/土楼住居と集落(片山和俊)/街と建築[客家と関わりの深い街](片山和俊・稲葉唯史)/生活と道具(尾登誠一)など、 248ページ。 ……………………… 九龍城; 宮本隆司、『九龍城砦』、ペヨトル工房、1988 差込に村松伸「九龍城砦」を掲載 同じ写真家による→こちらを参照:「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「vi. 廃墟など」 中村晋太郎、『最期の九龍城砦』、新風舎、1996 グレッグ・ジラード、イアン・ランボット、尾原美保訳、吉田一郎監修、『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』、イースト・プレス、2004 原著は Greg Girard, Ian Lambot, City of Darkness. Life in Kowloon Walled City, 1993/2003 序文(グレッグ・ジラード)/“魔窟”九龍城(ピーター・ポパム)/水の供給(チャールズ・ゴダード)/中国の香港出先機関を取り囲んだ要塞(ジュリア・ウィルキンソン)/九龍城・我が故郷(リョン・ピン・クワン)/警察の巡回/立ち退き処分(チャールズ・ゴダード)など、 216ページ。 ……………………… 産業建造物など; 岡田昌彰、『テクノスケープ 同化と異化の景観論』(景観学研究叢書)、鹿島出版会、2003 序章/テクノスケープの発見/テクノスケープの諸相/テクノスケープの理論/景観異化の方法/テクノスケープの展望など、 190ページ。 以下、写真集など; 柴田敏雄、『日本典型』、朝日新聞社、1992 84ページ。 ジェームズ・エンニヤート「壮麗なる運命のテラス」を収録 『ランドスケープ - 柴田敏雄』展図録、東京都写真美術館/旅行読売出版社、2008 もう一つの風景写真 - 柴田敏雄論(飯沢耕太郎)// color/B&W/night// 選ばれた風景(藤村里美)など、 84ページ。 畠山直哉、『LIME WORKS』、シナジー幾何学、1996 120ページ。 『畠山直哉』写真展図録、岩手県立美術館、国立国際美術館/淡交社、2002 ライム・ワークス/ライム・ヒルズ/ブラスト/タイトルなし/大阪 1998-1999/タイトルなし 1989-2001/川の連作/アンダーグラウンド/アンダーグラウンド/ウォーター/光のマケット/スロー・グラス/等高線// 畠山直哉 もののなりゆき、ことのなりゆき(島敦彦)/Keep Kicking Your Stones 畠山直哉、生成する輪郭、稜線(菅啓次郎)/石灰石鉱山を訪ねる(加藤俊明)など、 176ページ。 同じ写真家による→こちらを参照:「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「地下など」 『ランド・オブ・パラドックス』展図録、砺波市美術館、芦屋市立美術博物館、新潟市美術館/淡交社、1997 - 序 - パラドックスを越えて(河﨑鉱一)/二度と戻らない景色 - 新しい風景写真に関する考察(アンディ・グルンドバーグ)/ランド・オブ・パラドックス(福のり子)// 作品;雑賀雄二/畠山直哉/小林のりお/山根敏郎など、 112ページ。 金瀬胖、『ZONE - 終の国 -』、金瀬胖写真事務所、1999 108ページ。 西谷修「瞬間を強奪する 金瀬胖写真集に寄せて」を掲載 中田聡一郎、『奥飛騨の鉱山』、海拓舎、2001 92ページ。 石井哲・写真、大山顕・文、『工場萌え』、東京書籍、2007 工場グラビア/工場鑑賞ガイド/工場鑑賞の基礎知識など、112ページ。 萩原雅紀、『ダム』、メディアファクトリー、2007 萩原雅紀、『ダム2』、メディアファクトリー、2008 大山顕、『ジャンクション』、メディアファクトリー、2007 トマ・ジョリオン、岩澤雅利訳、『世界の美しい廃墟』、パイ インターナショナル、2015 原著は Thoma Jorion, silencio, 2013 もう一つのアメリカ/忘れられた宮殿/ソビエトを求めて/色あせた革命/コンビニ/シレンシオなど、 216ページ。 全6章中第4章「色あせた革命」がもっぱら産業建造物の廃墟を扱っています。最終章もその比率が高いか。 なお第4章にも日本で撮影された写真が何点かありましたが、続く第5章はもっぱら日本に取材しています。ただしコンビニの廃墟が取りあげられているわけではありません。 また産業建造物ではありませんが、第2章では主としてイタリアの廃館の写真をいくつも見ることができます。『リサと悪魔』(1973)や『処女の生血』(1974)などといったイタリアの怪奇映画が思いだされずにはいないことでした。 産業建造物というのとのは違いますが; 勝田尚哉、『建設中。』、グラフィック社、2017 日本の軍事建造物; 安島太佳由、『要塞列島 日本への遺言 安島太佳由写真集』、窓社、2008 戦争指導者たちの館/激戦と前線基地の島 硫黄島・父島・母島/本土決戦に向けて 九州・沖縄4/天然の地形を活かした要塞群 中国・四国/第二の大本営遷都と決戦準備 関西/工場疎開と地下壕 東海・北陸・甲信越/帝都の守り 関東/最果ての要衝 北海道・東北など、 260ページ。 安島太佳由、『訪ねて見よう! 日本の戦争遺産』(角川SSC選書 065)、角川書店、2009 序章 日本各地に残っている戦争の痕跡/沖縄・九州地方に残る戦争遺産/中国・四国地方に残る戦争遺産/近畿地方に残る戦争遺産/中部地方に残る戦争遺産/東京都に残る戦争遺産/関東地方に残る戦争遺産/東北・北海道地方に残る戦争遺産/最後に 「戦跡を訪ねる旅を終えて」など、 240ページ。 ……………………… 大谷採石場; 相澤正行、『写真集 大谷 その識られざる世界』、自家版、1977 64ページ。 小泉隆、『大谷採石場 不思議な地下空間』、随想舎、2010 80ページ。 写真=藤塚光政、文=毛綱毅曠、『不知詠人 詠み人知らずのデザイン』、TOTO出版、1993、pp.146-157:「ジオフロントの先駆 大谷の地底大伽藍[宇都宮]」、「地底都市の憂鬱」、p.334:「写真注記+参考資料 大谷の地底大伽藍」 ……………………… 軍艦島; 雑賀雄二、『軍艦島 眠りのなかの覚醒』、淡交社、2003 1986年刊本の改訂版 作品// 奇妙なモノたち(笠原美智子)/追想・軍艦島/眠りのなかの覚醒/資料など、 144ページ。 写真=藤塚光政、文=毛綱毅曠、『不知詠人 詠み人知らずのデザイン』、TOTO出版、1993、pp.304-311:「集積都市のチン没 軍艦島[長崎・玄界灘]」、「近代日本のエピトーメ」、pp.335-336:「写真注記+参考資料 軍艦島」 小林伸一郎、『NO MAN'S LAND 軍艦島』、講談社、2004 144ページ。 『ワンダーJAPAN』、no.3(三才ムック vol.141)、2007.1.1、pp.6-47:「海上廃都 軍鑑島」 オープロジェクト、『軍艦島全景』、三才ブックス、2008 住宅棟アーカイブズ/大正時代/昭和時代(戦前)/昭和時代(戦後)/昭和時代(高度成長期)/軍艦島名所散策/鉱業所アーカイブズ/アンダーグラウンドなど、 160ページ。 黒沢永紀、『軍艦島入門』、実業之日本社、2013 黒ダイヤの島/軍艦島 その特殊性/軍艦島 驚きの暮らし/軍艦島のすごい建物/軍艦島ミステリー/知られざる秘話/軍艦島、未来へ// 軍艦島へ行くために、など、 160ページ。 ……………………… ベルント&ヒラ・ベッヒャー; Bernt & Hilla Becher, Framework Houses of the Siegen Industrial Region, Schirmer/Mosel, München, 1977 『ジーゲン工業地帯の枠組み家屋』 350点掲載 Bernt & Hilla Becher, Fördertürme Chevalements Mineheads, Museum Folkwang Essen, ARC / Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, Castello di Rivoli / Torino, Musée d'Art Moderne de la Ville de Liège, 1985 『捲き上げ塔』 224ページ →こちらで引きあいに出しました(『執念のミイラ』(1944)の頁 Bernt & Hilla Becher, Wassertürme Château d'eau, Kunstverein, München / Magasin, Centre National d'Art contemporain de Grenoble, 1988-89 『給水塔』 223点掲載 Bernt & Hilla Becher, Hochöffen, Schirmer/Mosel, München, 1990 『熔鉱炉』 223点掲載 Bernt & Hilla Becher, Pennsylvania Coal Mine Tipples, Schirmer/Mosel, München, 1991 『ペンシルヴァニアの炭坑、石炭選別場』 99点掲載 Bernt & Hilla Becher, Gas Tanks, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1993 『ガス・タンク』 102点掲載 針生一郎、「ベッヒャー夫妻 工業建造物の形態学者 この風変わりな芸術家たち 3」、SD、1973.4、pp.102-110 『コロキウム・ベッヒャー』、川崎市民ミュージアム、1996 『ドイツ現代写真展 遠・近 ベッヒャーの地平』に際して刊行 モダニズムを越えて - ベッヒャーの地平-(深川雅文)/ベルント&ヒラ・ベッヒャーの写真について(ズザンネ・ランゲ)/Es denkt, Es blitzt, Es sieht - 無人の風景とベルント&ヒラ・ベッヒャー-(清水穣)/静物、形態、色彩 ベルント&ヒラ・ベッヒャーの産業建造物とクラウス・ゲーディケとトーマス・ルフの静物(ルペルト・プファブ)/ベルント&ヒラ・ベッヒャー - 近代社会のモルフォロギ- -(山本和弘)/ベッヒャーと作品とのあいだ(千葉成夫)/遠・近(ヴルフ・ヘルツォーゲンラート)/ベルント/ヒラ・ベッヒャーの作品……視覚の往還(千葉成夫)など、 168ページ。 ……………………… 学校など; 『木造校舎の思い出 芦澤明子写真集 関東編』、情報センター出版局、1996 184ページ。 『木造校舎の思い出 芦澤明子写真集 近畿・中国編』、情報センター出版局、1998 208ページ。 ……………………… ボマルツォの〈聖なる森〉 - まずは; 澁澤龍彦、『幻想の画廊から』、1967 所収の「ボマルツォの『聖なる森』」 澁澤龍彦、『ヨーロッパの乳房』、1973 所収の「バロック抄-ボマルツォ紀行」 澁澤龍彦については→こちらを参照:「通史、事典など」の頁の「おまけ」 澁澤の参照源の一つであるマンディアルグが序文を寄せた写真集は André Pieyre de Mandiargues, photographies de Glasberg, Les monstres de Bomarzo, (La Galerie en images), Grasset, 1957 120ページ。 序文の訳が アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ、澁澤龍彦訳、『ボマルツォの怪物』(河出文庫 ヒ 2-1)、河出書房新社、1999 に収録 1979年刊本の文庫化で、他に; 黒いエロス/ジュリエット/異物/海の百合/イギリス人(抄) を所収 マリオ・プラーツ、白崎容子訳、「ボマルツォの怪物」(1949)、若桑みどり・森田義之・白崎容子・伊藤博明訳、『官能の庭 マニエリスム・エンブレム・バロック』、ありな書房、2000、pp.115-122 原著は Mario Praz, "I mostri di /Bomarzo", 1949, Il Giardino dei Sensi : Studi sul manierismo e il barocco, 1975 同書からは→こちらにも挙げています:「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「迷宮など」の項 川田喜久治、「聖なる森と蠟人形館 個展の背景=ある世界」、『美術手帖』、no.295、1968.3、pp.146-153 同じ著者による→こちらを参照:「怪奇城の外濠」の頁の「iv. 城など」 また 『化け物 想像力が生み出す異世界の住人』、青森県立美術館/青幻舎、2015、pp.111-128:「SECTION 4:化け物たちの棲むところ」中の cat.nos.171-186 は「川田喜久治 《聖なる森》」 江原順、「幻想建築の旅 - ボマルツォの怪物 -」、『藝術新潮』、vol.24 no.10、1973.10、pp.177-182 板東通世、写真:中村保、「山岳都市 ボマルツォ 怪物公園 ユートピア共同体への夢 8」、『みづゑ』、no.845、1975.8、pp.68-87 安藤哲行、「既視のボマルツォ」、『ユリイカ』、第27巻第2号、1995.2:「特集 マニエリスムの現在」、pp.197-215 聖なる森の謎/「聖なる森」の透視図/怪物たちの、聖なる森の意味/新たな神話の創造 尾形希和子、「 ボマルツォは反庭園か/オルシーニ家とボマルツォ/ヴィチーノ・オルシーニ公/庭園のオリジナルの姿/ボマルツォの庭のプログラム/ヴィチーノにとっての「 ダニエル・アラス、吉田典子訳、『モナリザの秘密 絵画をめぐる25章』、白水社、2007、pp.157-169:「第14章 マニエリスム小史」中の pp.166-168 ミヒャエル・ニーダーマイヤー、濱中春・森貴史訳、『エロスの庭 愛の園の文化史』、2013、pp.180-187 櫻井麻美、「ボマルツォの『聖なる森』を訪ねて」、『紀尾井論叢』、no.1、2013.7.19、pp.63-72 [ < 上智大学学術情報リポジトリ ] 伊藤博明、「第6章 ボマルツォの驚異 - 『聖なる森』のマニエリスム的世界」、金山弘昌責任編集、『憧憬のアルストピア パラッツォ・デル・テ『クピドとプシュケの間』からボマルツォ『聖なる森』へ』(イタリア美術叢書Ⅲ)、ありな書房、2020、pp.215-274+註:pp.305-311 ボマルツォの「聖なる森」の再生/ボマルツォの「聖なる森」の発見/ボマルツォの「聖なる森」の伝説化と新たな探求/ボマルツォ公ヴィチーノ・オルシーニの生涯/スフィンクス/「聖なる森」案内/「聖なる森」と怪物たち →アリストテレス『ニコマコス倫理学』への挿絵 《スフィンクスと理性の擬人化》(1500頃)の頁の「Cf.」で参照しました。 Mary A. Platt, Il Sacro Bosco : The Significance of Vicino Orsini's Villa Garden at Bomarzo in the History of Italian Renaissance Garden, A Thesis submitted to Michigan State University, 1986, UMI Dissertation Infrormation Service 『聖なる森 イタリア・ルネサンス庭園史におけるボマルツォのヴィチーノ・オルシーニ荘庭園の意義』 序論/今日のボマルツォ訪問/ボマルツォの歴史/「聖なる森」の主:ヴィチーノ・オルシーニとボマルツォの庭園/ルネサンス庭園における荒々しく幻想的な要素の使用/結論など、 128ページ。 Emanuela Kretzulesco-Quarranta, Les jardins du songe. "Poliphile" et la mystique de la renaissance, 1986, pp.283-297: "2 - II. Bomarzo. Le bois sacré" 『夢の庭 「ポリフィリ」とルネサンスの神秘学』、第2部第2章「ボマルツォ 聖なる森」 Horst Bredekamp, Fotografien von Wolfram Janzer, Vicino Orsini und der heilige Wald von Bomarzo. Ein Fürst ls Künstler und Anarchist, Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms, 1985/1991 『ヴィチーノ・オルシーニとボマルツォの聖なる森 芸術家・無政府主義者としての領主』 第1部 写真 第2部 テクスト ボマルツォという謎// ヴィチーノ・オルシーニ;若年/兵士としての経歴/ボマルツォへの撤退/官能の力// 庭園と宮殿の建造;庭園設計者の哲学/自由彫刻の心理学/内的な感覚喪失/外的な名声// 銘;隠されたもの/森のプロパガンダ/宮殿の名声// 願望空間;新アルカディアのモティーフ/アメリカのヴィジョン/永遠と宇宙/冥界と極東// ボマルツォの名声と侮蔑など、 334ページ。 →『生きた屍の城』(1964)の頁も参照 同じ著者による→そちらを参照:「バロックなど(17世紀)」の頁の「viii. ライプニッツ(1646-1716)など」 ブレーデカンプについて; 加藤哲弘、『美術史学の系譜』、中央公論美術出版、2018、第5章第3節「ブレーデカンプ」 また ムヒカ=ライネス、『ボマルツォ公の回想』、1984 ……………………… パラゴニア荘; Brassaï, "La Villa Palagonia : Une curiosité du Baroque Sicilien", Gazette des Beaux-Arts, 1962, tome 60, pp.351-364 「パラゴニア荘 シチリア・バロックの名所」 George Levitine, "Les monstres du prince Palagonia : Leurs critiques et leurs admirateurs", Gazette des Beaux-Arts, no.1140, 1964.1, pp.13-24 「パラゴニア公の怪物たち:その批判者たちと讃美者たち」 ……………………… 綺想建築、その他; Michael Schuyt, Joost Elffers, text by George R. Collins, Fantastic Architecture. Personal and Eccentric Visions, Harry N. Abrams, New York, 1980 『幻想建築 個人的で奇矯なヴィジョン』 序(Michael Schuyt, Joost Elffers)/幻想建築( George R. Collins)/芸術家たち/城と塔/…としての建物/幻視者たち/通常のものでない素材/内部-外部/庭など、 248ページ。 Photographed & described by Lucinda Lambton, An Album of Curious Houses, Chatto & Windus, London, 1988 『奇異な家のアルバム』 160ページ。 John Beardsley, Gardens of Revelation. Environments by Visionary Artists, Abbeville Press, New York, London & Paris, 1995 『黙示の庭 幻視的芸術家たちによる環境作品』 序:黙示の庭/「欲望の驚くべき沈殿」/神と郷のために/聖なる書物のグロッタ/愛する泉と生きる権利/精霊たちの森、夢の箱舟など、 224ページ。 Robert Peacock with Annibal Jenkins, Paradise Garden. A Trip through Howard Finster's Visionary World, Chronicle Books, San Francisco, 1996 『楽園の庭 ハワード・フィンスターの幻視的世界の旅』 120ページ。 Idea and photographs by Deidi von Schaewen, texts by John Maizels, Fantasy Worlds, Taschen, 1999 『幻想世界』 序/ヨーロッパにおける環境作品/アメリカにおける環境作品/アジアとアフリカにおける環境作品など、 340ページ。 Gordon Taylor and Guy Cooper, Gardens of Obsession. Eccentric and Extravagant Visions, Weidenfeld & Nicolson, 1999 『妄執の庭 奇矯で法外なヴィジョン』 序/刈込と接ぎ木/庭と「緑」の建築/花々に憑かれて/稀少植物と巨大野菜/彫刻/庭園におけるシュルレアリスム/芸術家の庭/自己学習者の芸術/形式的庭園など、 192ページ。 Stephan Trüby, "The Corridor-Cell Complex", Rem Koolhaas et al., Elements of Architecture, 2014/2018, pp.1310-1315 (pp.58-63) ; '3. Welbeck Abbey and the 5th Duke of Portland : at home in the Corridor-Cell Complex' 『建築の諸要素』、「廊下」のセクション中のシュテファン・トゥリュービー「廊下=小房複合」、第3章「ウェルベック修道院と第五代ポートランド公爵:廊下=小房複合の中でくつろいで」 Photos : Hans Werlemann, "Welbeck Abbey", op.cit., pp.1316-1333 (pp.64-81) 「ウェルベック修道院」、写真:ハンス・ヴェルレマン Stephan Trüby, Geschichte des Korridors, 2018, pp.226-231, 249-254: "IV.III. Psychopathologien des Puritanismus : Die Welbeck Abbey des fünften Herzogs von Portland und Sarah Winchesters 'Mystery House' im Vergleich" 『廊下の歴史』、第4章3節「ピューリタニズムの精神病理学:第五代ポートランド公爵のウェルベック修道院、サラ・ウィンチェスターの『 Elements of Architecture の p.1311(59) の註93 および Geschichte des Korridors の p.227 註96 に挙げられていたのが; Derek Adlam., Tunnel Vision. The Enigmatic 5th Duke of Portland, The Harley Gallery, Welbeck, 2013 『隧道幻視 謎めく第五代ポートランド公爵』 謎めく第五代ポートランド公爵/1869年から79年までのウェルベックにおける洗濯女中としての生活についてのエリザベス・バトラーの話/エピローグなど、 40ページ。 A5大(20.9 x 14.7 cm)の小冊子です。写真や図版は豊富に掲載されていますが、トンネル内のものは見あたらないので、上掲のヴェルレマン撮影の写真等を参照ください。 同じく Geschichte des Korridors の p.231 註105 に挙げられていたのが; Cynthia Anderson., The Winchester Mystery House. The Mansion Designed by Spirits, The Winchester Mystery House, California, 1997 『ウィンチェスター・ミステリー・ハウス 霊たちによって設計された屋敷』 神秘の女性/ 美しい、しかし奇怪な コラム;数13 革新的なウィンチェスター夫人 謎めいた舞踏室の窓 屋敷の修復、保護、維持/ 庭園と構内/ 愉快なことと謎めいたこと コラム;最後の問い/ ウィンチェスターの歴史的小火器と骨董製品博物館など、 48ページ。 A4変型となるのでしょうか、27.8 x 21.0cm とサイズは大きくなりましたが、ページ数からして、やはり浩瀚とはいいがたい。それでも建物内外の写真がぼちぼち掲載されています。 →こちらでも挙げました:『たたり』(1963)の頁の「おまけ」 ウィンチェスター・ハウスについては、上の「住宅その他」の項で挙げた八木幸二・田中厚子、『アメリカ木造住宅の旅 建築探訪 3』(1992)でも触れられていました。 式場隆三郎、藤森照信、赤瀬川原平、式場隆成、岸武臣、『二笑亭綺譚 50年目の再訪記』、求龍堂、1989 二笑亭綺譚(式場隆三郎、1939/1965);発端・電話事件/赤木城吉小伝/二笑亭の由来/異様な外観/不思議な間取/黒板に残された文字/節孔窓/和洋合体風呂/昇れぬ梯子/遊離した厠/鉄板の目隠し/土蔵裏の祠/天秤堂/使えぬ部屋/巨大な擂木/二笑亭主人語録/病気の診断/芸術としての二笑亭/生活の反省// 二笑亭後日譚// 跋・二笑亭の建築;跋(柳宗悦)/二笑亭の建築(谷口吉郎)/あとがき// 50年目の再訪記;二笑亭主人遺聞(式場隆成)/二笑亭再建せり(藤森照信)/小説 毛の生えた星(赤瀬川原平)/(付)海外旅行記(渡辺金藏)など、 320ページ。 岩井寛、『境界線の美学 異常から正常への記号』、造形社、1977、pp.115-141:「変容の解析 - 『二笑亭』・『イシドールの城』・『ユンカーの家』の空間と変容 -」 上の本で二笑亭が扱われていたことを思いださせてくれたのが; 種村季弘、『書物漫遊記』(ちくま文庫 た 1-2)、筑摩書房、1986、pp.78-88:「6 開かされた箱 坂根巌夫『遊びの博物誌』」 1979刊本の文庫化
荒俣宏、『パラノイア創造史』、1985、pp.215-232:「13 奇妙な家を建てようとした男 - 赤木城吉」 あるインターリュード/世界の所有/二つの笑い 東野芳明、「奇態な塔 ワッツタワー L・A物語」、『美術手帖』、no.220、1963.5、pp.19-28 ウンベルト・エーコ、片岡信訳、「 原著は Umberto Eco, "Enchanted Castles", Travels in Hyperreality, 1986 『サー・ジョン・ソーン美術館[19世紀] 磯崎新の建築談義 #11』、六耀社、2004 建築談義 磯崎新(インタビュアー 五十嵐太郎);なぜ、19世紀の建築としてサー・ジョン・ソーン美術館を選んだのか/サー・ジョン・ソーン美術館を実際に見る/サー・ジョン・ソーン美術館 朝食室/絵画室/ジョン・ソーンの天井/第六のオーダー/ダリッチ・ギャラリー/新古典主義/ゴシック・リヴァイヴァル/グランドツアー/サー・ジョン・ソーンの仕事/ジョン・サマーソン『古典主義建築の言語』/建築のオーセンティシティ/スーパーデプス/フォトグラフィは真を写すのか/コレクション/影/鏡/あわい/廃墟// 写真 篠山紀信(解説:菊地誠)など、 184ページ。 鈴木博之、藤森照信、隅研吾、松葉一清、山盛英治、『奇想遺産 世界のふしぎ建築物語』、新潮社、2007 奇景奇観/奇塔奇門/奇態/奇智/数奇/神奇/新奇叛奇など、 160ページ。 鈴木博之、藤森照信、隅研吾、松葉一清、木村伊量、竹内敬二、山盛英治、『奇想遺産Ⅱ 世界のとんでも建築物語』、新潮社、2008 神奇/奇景/奇塔奇門/奇態/奇智/数奇/新奇叛奇など、 160ページ。 田中純、『冥府の建築家 ジルベール・クラヴェル伝』、みすず書房、2012 序// メタモルフォーゼ;死の舞踏(1902~07年)/放蕩者たちの島(1907~11年)/アーシア断章 - 日記と手紙から/オリエントへ(1911~14年)// アヴァンギャルド;エキセントリック(1914~17年)/未来派(1917~18年)/メタフィジカ(1918~20年)// ミステリウム;塔と洞窟(1920~25年)/友と敵(1923~25年)/睾丸と卵(1925~27年)など、 540ページ。 →こちらにも挙げています:「エジプト」の頁の「おまけ」 同じ著者による→そちらを参照:「天使、悪魔など」の頁の「i. 天使など」の冒頭 石山修武編著、毛綱毅曠著、佐藤研吾註釈、『異形建築巡礼』、国書刊行会、2016 「異形」の再発見とその正統性 - 日本近代建築への見直しへの一石(ラ・パボーニ、アート・ガーデン、伴野一六邸ほか);〈異〉と〈位〉の空間学 - ラ・パボーニ アート・ガーデン(毛綱モン太)/伴野一六邸異聞(石山)// 螺旋・アニマ巡礼 - 建築の始原へタイム・トリップ(蘭庭院栄螺堂、旧正宗寺三匝堂ほか);江戸三大奇館その一 - 栄螺堂(毛綱)/栄螺堂幻想辺(石山)// 神々の宿る地形・建築 - 日本的なるものの別系統(三仏寺投入堂、笠森寺、岩室山観音堂ほか);江戸三大奇館その二 - 板東霊場 笠森寺大悲閣(毛綱)/巡礼パノラマ空間(石山)// 機械のはじまりへ - 日本の遊戯機巧(正久山妙立寺(忍者寺)、二条陣屋ほか);江戸三大奇館その三 - 妙立寺(毛綱)/機巧の薄暗がりを抜けること(石山)// 擬洋風建築 - 日本近代建築の伏流(済生館、開智学校、盛美園、弘前教会ほか);異人館(毛綱)/職人気質の華のなかを(石山)// 遊行者集団の人力掘削建築 - 日本の仏を闇に視る(田谷山瑜伽洞ほか);〈曼荼羅起〉瑜伽洞(毛綱)/田谷山瑜伽洞闇の内(石山)// 異形の地平から - 日本近代建築を再考する(吉備津神社、閑谷学校、鳳来寺、方広寺、二笑亭、岩窟ホテルほか);〈位〉と〈異〉の領域学(毛綱)/BARRACK(石山)// メビウスの環、そして時代は廻る - 近代建築のもう一つの回路を求めて;はじめとおわり(毛綱)/おわりのはじめに BARRACK 論そして異境へ(石山)// 〈書き下ろし〉異形の建築群(または建築の異形群)(安藤忠雄、毛綱モン太『反住器』、渡辺豊和『ガキの舎』、六角鬼丈『クレヴァスの家』)(石山)// あとがきに代えて 異形の旅 - 毛綱モン太と久しぶりに会う(石山)など、 338ページ。 『建築』誌に1973-75年連載した「異形の建築」に書き下ろし等を加え、写真を新たに編集したもの 石山修武による→一つ飛ばしてその次に挙げる本を参照:『セルフビルド』、2008 毛綱毅曠による→次に挙げるの本、および一つ飛ばしてその次の本とともにこちら(「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「v. 建築など」)や、またそちら(「中国」の頁の「i. 概説、通史など」の項の内、三浦國雄『中国人のトポス』(1988)掲載の対談)も参照 合わせて; 写真=藤塚光政、文=毛綱毅曠、『不知詠人 詠み人知らずのデザイン』、TOTO出版、1993 UFO仕様〈地球驚異巡礼〉へのお誘い(荒俣宏)// モンゴロイドのインナー・コスモス サイウーテの宇宙卵[ペルー・クスコ]/UFOも表敬訪問する天空階段 ジャイブールの星神社[インド・ラージャスターン州]、デリーの星神社[インド・ハリヤーナー州]/対空メッセージの建築術 魔都のフラックトゥルム[ウィーン]/湾岸のループ・ファンタジア 大黒インターチェンジ[横浜ベイブリッジ]/高キニノボル鉄の魔術師 エッフェルのエレベーター塔[リスボン]/終の住処で夢飛行 ドモーンのコックピットハウス[ブラジル・ペトロポリス]/天空の立体マンダラ 白居寺・超宗教の蓮華出水形[チベット・ギャンツエ]/アマゾンの悲しき成金都市 マナウスの大市場[ブラジル・アマゾン]/チャオプラヤ河の曳かれ船 艀船[バンコク]/黄河文明のリゾーム住居 黄土のヤオトン集落[中国・河南省]/雨期の浮島 三角州のミステリー・アイランド[メキシコ西部]/ジオフロントの先駆 大谷の地底大伽藍[宇都宮]/消滅寸前バラックコロニー 圓環夜市[台湾・台北]/時の斜塔 トウルク・インタンの巨根[マレーシア]/メドゥーサの目覚め イスタンブールの地下水殿[トルコ]/ 写真注記+参考資料(藤塚光政)など、 342ページ。 石山修武=文、中里和人=写真、『セルフビルド SELF-BUILD 自分で家を建てるということ 、交通新聞社、2008 はじめに/ワビ、サビ、コンテナ飲み屋/モバイル電化ハウス/川合邸/掩体壕/キジセンター/完全0ハウス/サーファーの家/秘密の庭園/磯崎新の隠れ家/開拓者の家/山あげ祭/貝がら公園/世田谷村/神長官守矢史料館/船上にて/松浦武四郎の一畳敷(泰山荘)/オープン・テクノロジー・ハウス/バー・トタン/雪原のスノーボート/マザー・テレサの「死を待つ人の家」/トンレサップ湖に浮く家/セルフビルド・イン・ジャズ/ひろしまハウスでレンガ積み/増殖するガレージ/セルフビルドする町/恐竜ロボット/500万ハウス/世界でいちばん小さな家など、 138ページ。 石山修武による→二つ上に挙げた本を参照:『異形建築巡礼』、2016 中里和人による→こちらを参照:本頁上掲の「路地など」の項 少し遡って; 毛綱毅曠、『七福招来の建築術 造り、棲み、壊すよろこび』(KAPPA SCIENCE ⑤-50)、光文社、1988 まえがき/英雄豪傑の見果てぬ夢/手造りに狂う人びと/建築は鬼が造る/快感の「嬉し泣き住宅」のために/都市は七福神漬けである/宇宙の「記憶」が建築を造る/エピローグ みんながヒトラー、など、 248ページ。 この本のことは下の「郵便夫シュヴァルの理想宮」の項に挙げた有栖川有栖の『双頭の悪魔』(1992/1999)で知ったのですが、そこでの話題だったシュヴァルの理想宮については pp.78-80 でとりあげられています。そのなかで「実物を見学した建築批評家の下村純一サン」(p.78)に触れていましたが、まずはやはり『双頭の悪魔』で書名を見かけたのが; 下村純一、『不思議な建築 甦ったガウディ』(講談社現代新書 820)、講談社、1986 自然と生物 - 建築に息づく不思議感覚;甦ったガウディ/ガウディとポスト・モダン/端整な白い箱たち/不格好の魅力/アナロジーの妙// 洞穴 - 甦る太古の揺籃;現代版ラスコー/洞穴をめぐる二つのイメージ/人間の自己空間/さまざまな洞穴空間/暗闇と光と/生きものの 肉体 - 空間を包み込んだ壁;呼吸する建築/皮膚としての壁/ガウディとドラゴン/肉の匂い/建築動物図鑑/人の顔// 樹木 - 成長する構造;放物線構造の意味/植物的生命の空間/ガウディの螺旋/形態と力// 物の塊 - 生命を宿す造形;裸の鉄/映し出された個人/かけらからの出発/「 232ページ。 シュヴァルの理想宮については、pp.179-182 / 写真114-117、pp.195-197。 同じ著者による→こちらを参照:「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「建築と写真など」の項 古庄弘枝、『沢田マンション物語』、情報センター出版局、2002 「笑みがこぼれるマンション」の理由/「奇才誕生」秘話/建てては売る新婚時代/悲願のマンション建設の裏側で/沢田夫妻が語りかけることなど、 302ページ。 加賀屋哲朗、『沢田マンションの冒険 驚嘆!セルフビルド建築』(ちくま文庫 か 66-1)、筑摩書房、2015 文庫版まえがき// 沢田マンションという建築物/沢田マンションの歩き方 - 沢マンを読み解く13のキイワード/沢田マンションに暮らす人々と生活/沢田マンション図面集成// 単行本あとがき/文庫版あとがき/解説 沢田マンション探訪(初見学)/エッセイ 「必ずあんたは作りきるろう」と言われた夜(岡啓輔)/帯文(奈良美智)など、 304ページ。 2007年刊行の『沢田マンション超一級資料 - 世界最強のセルフビルド建築探訪』を改題・加筆して文庫化 沢田マンションのことは、 有坂蓉子、『ご近所富士山の「謎」 富士塚御利益散策ガイド』(講談社+α新書 431-1 D)、講談社、2008 富士塚へようこそ/厳選! 富士塚36基 登拝ガイド/イベントで楽しむ富士塚など、 244ページ。 →こちらでも触れました:「津の築山遊具など」の頁 富士山つながりということで→そちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」の「庭園など」の項)に挙げた牛田吉幸、『名古屋の富士山すべり台』(2021)も参照 富士塚については、「階段で怪談を」の頁の「文献等追補」中の「註15: 北澤憲昭、『眼の神殿』、美術出版社、1989、pp.15-108:「第1章 『螺旋展画閣』構想」 中の pp.54-55:「江戸の人造富士」でも取りあげられていました。 ……………………… 郵便夫シュヴァルの理想宮 - まずは; 澁澤龍彦、『幻想の画廊から』、1967 所収の「幻想の城 ルトヴィヒ二世と郵便屋シュヴァル」 澁澤龍彦については→こちらを参照:「通史、事典など」の頁の「おまけ」 里見宗次、「夢の宮殿 郵便配達夫シュヴァルの情熱物語」、『美術手帖』、no.245、1964.12、pp.17-21 ベアトラン・レゾン、太田泰人訳、「郵便配達夫シュヴァルの『理想宮』 ALL THAT ART 12」、『美術手帖』、no.495、1982.4、pp.220-227 とこうする内に、ついに日本語で読めるようになったまとまった文献が; 岡谷公二、『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』、作品社、1992 オートリーヴ/単独歩行者の夢/村の気違い/「終わりなき静寂と休息の墓」// 理想宮案内;東の正面 生命の泉~知恵の泉~聖エメデの洞窟、「自然の神殿」、三人の巨人~バルバリーの塔/西の正面 ヒンズーの寺院、ホワイトハウス他/南の正面 「大洪水前の博物館」~オークの木/北の正面 洞窟群~動物たちと怪物たち/回廊 北の迷宮、南の迷宮/空中庭園/シュヴァル動物園// 死後の栄光/三人の大無意識家 シュヴァル~ルソー~ルーセルなど、 248ページ。 許光俊、「庭園料理ア・ラ・シュヴァル-ピエール・ガニェールのムニュ・ド・ジェオグラフィ」、『ユリイカ』、vol.28 no.5、1996.4:「特集 空中庭園」、pp.256-261 ヤノベケンジ、「フェルディナン・シュバル『理想宮』 妄想の未来へ 十選 3」、『日本経済新聞』、2004.6.22、文化40面 南後由和、「郵便配達夫シュヴァルの理想宮 - シチュアシオニストが愛した建築」、『季刊 d/SIGN デザイン』、no.16、2008.8:「特集 廃墟と建築」、pp.44-48 シチュアシオニストの「転用」/シュヴァルの理想宮の両義性 - 影、永久曲線/石の海の隆起、採石場の迷宮化/郵便配達夫≒建築家 Maurice Verillon, "Le Palais idéal du facteur Cheval", Gazette des Beaux-Arts, no.1220, 1970.9, pp.159-184 「郵便配達夫シュヴァルの理想宮」 Jean-Pierre Jouve, Claude Prévost, Clovis Prévost, Le Palais idéal du facteur Cheval/ Quand le songe devient la réalité, Éditions du Moniteur, Paris, 1981 『郵便配達夫シュヴァルの理想宮 夢が現実になる時』 フェルディナン・シュバルの手紙、1897年/修復のために(ジャン=ピエール・ジューヴ)/夢の根:1836-1879(クロード・プレヴォ)/夢から現実へ:1879-1924(クロード&クロヴィス・プレヴォ)// 附録;占星術的解釈への入口(ロズリーヌ・ブヴィエ、ボブ・デュラン)/郵便配達夫シュヴァルの自伝など、 304ページ。 劇映画になっていました; 『シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢』、2018、監督:ニルス・タヴェルニエ 作中でシュヴァルの理想宮が言及されるのが; 有栖川有栖の『双頭の悪魔』(創元推理文庫 M あ 2-3)、東京創元社、1999 1992年刊本の文庫化
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| おまけ 美術方面から(追補:→「怪奇城の肖像(前篇)」の頁でも挙げました); 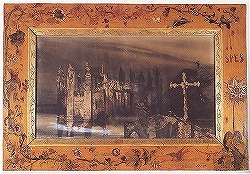 ヴィクトル・ユゴー 《十字架のある城》 1850年 * 画像をクリックすると、拡大画像とデータが表示されます。 バンド・デシネから; ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画、古永真一・原正人訳、『闇の国々』、小学館集英社プロダクション、2011 シリーズの原著は Benoit Peeters et François Schuiten, Les cités obscures, 1983- Préface 日本語版に寄せて(ブノワ・ペータース)// 狂騒のユルビカンド(1985)/塔(1987)/傾いた少女(1996)// ブノワ・ペータース インタビューなど、 400ページ。 ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画、古永真一・原正人訳、『闇の国々Ⅱ』、小学館集英社プロダクション、2012 サマリスの壁(1983)/パーリの秘密(1984-2001)/ブリュゼル(1992)/古文書官(1987)など、 288ページ。 ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画、関澄かおる・古永真一・原正人訳、『闇の国々Ⅲ』、小学館集英社プロダクション、2013 ある男の影(1999)/見えない国境(2002-2004)/エコー・デ・シテ(1993)// ペータース&スクイテン インタビューなど、 312ページ。 ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画、古永真一・原正人訳、『闇の国々Ⅳ』、小学館集英社プロダクション、2013 アルミリアへの道(1988) 傾いたメリー(1995)/月の馬(2004)/真珠(2010)// 永遠の現在の記憶(1993/2009)/砂粒の理論(2007-2008)// 富士山を待ちながら(2002)、など、 336ページ。
バンド・デシネついでに(→こちら:「エジプト」の頁の「おまけ」や、そちら(「近代など(20世紀~) Ⅴ」の頁の末尾)も参照)、「ルーヴル美術館 ニコラ・ド・クレシー、大西愛子訳、小池寿子監修、『氷河期』、小学館集英社プロダクション、2010 原著は Nicolas de Crécy, Période glaciaire, 2005 88ページ。 マルク=アントワーヌ・マチュー、大西愛子訳、小池寿子監修、『レヴォリュ美術館の地下 ある専門家の日記より』、小学館集英社プロダクション、2011 原著は Marc-Antoine Mathieu, Les sous-sols du Révolu. Extraits du journal d'un expert, 2006 68ページ。 荒木飛呂彦、『岸辺露伴ルーヴルへ行く』、集英社、2011 140ページ。 同じ著者による→こちらを参照:「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁の「xxiii. 日本の漫画、アニメーションなど」 エンキ・ビラル、大西愛子訳、小池寿子監修、『ルーヴルの亡霊たち』、小学館集英社プロダクション、2014 原著は Enki Bilal, Les fantômes du Louvre, 2012 144ページ。 同じ著者による→こちらを参照:「エジプト」の頁の「おまけ」 こちらは絵本; 菊地秀行作、Naffy 絵、『城の少年』、マイクロマガジン社、2020 同じ著者による→こちらを参照:「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁の「菊地秀行」の項 |
||||||||||||||||||||||
音楽方面から、まずは何より; コスモス・ファクトリー、『コスモス・ファクトリー』、1973(1) 1枚目となるB面いっぱいを占める「トランシルヴァニアの古城」、18分40秒。「死者の叫ぶ森」、「呪われた人々」、「霧界」、「トランシルヴァニアの古城」の4部構成で、第2部と第4部が歌入り。 いかにもいかにもという感じで、雨音に雷鳴がかぶさり、オルガンがうなります。メロトロンも鳴っています。 |
1.ヌメロ・ウエノ、たかみひろし、『ヒストリー・オブ・ジャップス・プログレッシヴ・ロック』、マーキームーン社、1994、pp.97-98。 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.44、2010.2、p.65。 →こちらも参照:「近代など(20世紀~ )」の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
次に; Esperanto, Dance macabre, 1974(邦題:エスペラント『エスペラント』)(2) のA面2曲目、"The Castle"(「城郭」)。 長めのインストゥルメンタル曲に前後をはさまれた、短いつなぎの曲ではありますが、とても印象的なメロディーを有しています。 |
2. 大鷹俊一監修、『ヤング・パーソンズ・ガイド・トゥ・プログレッシヴ・ロック』、音楽之友社、1999、p.115。 深見淳・松崎正秀監修、『UKプログレッシヴ・ロック メインストリーム・エディション~The Golden Era』(THE DIG presents Disc Guide Series #017)、シンコーミュージック、2004、p.91。 →こちらも参照:「アメリカ大陸など」の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
余談ですが、この曲のコーラス部分によく似たメロディーが、 Fireballet, Night on Bald Mountain, 1975(3) A面1曲目の"Les cathédrales"中に現われます。偶然の一致なのか引用なのか、あるいは共通の典拠があるのかは詳らかにしませんが、ちなみに、続く"Centurion (Tales of Fireball Kids)"では、 Quatermass, Quatermass, 1970(邦題:クォターマス『クォターマス』)(4) のB面1曲目"Gemini"(「ジェミニ」) の転換部でのリフが顔を出したりしています。 |
3. 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.58。 4. The Bible. rock magazine 04、ロックマガジン社、1981、p.76。『マーキー別冊 ブリティッシュ・ロック集成』、マーキームーン社、1990、p.39。 『ユーロ・ロック集成』、マーキームーン社、1987/90、p.214。 深見淳・松崎正秀監修、『UKプログレッシヴ・ロック メインストリーム・エディション~The Golden Era』(THE DIG presents Disc Guide Series #017)、シンコーミュージック、2004、p.106。 立川芳雄、『プログレッシヴ・ロックの名盤100』、リットーミュージック、2010、p.23。 岩本晃一郎監修、『ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック100』(Masterpiece Albums vol.2)、日興企画、2012、p.114。 →こちらにも挙げておきます:『宇宙からの侵略生物』(1957)の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
The Rolling Stones, Their Satanic Majesties Request, 1967(ローリング・ストーンズ、『サタニック・マジェスティーズ』) のA面2曲目、"Citadel"(「魔王のお城」、2分53秒。 同じアルバムから→こちら(「通史、事典など」の頁の「おまけ」)に挙げました。 Nox Arcana, Transylvania, 2005 ちなみに7曲目が"Castle Dracula"、2分56秒。 同じアルバムから→こちらを参照:「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁の「v. 鐘塔など」 別のアルバムから→そちらを参照:「近代など(20世紀~ ) Ⅳ」の頁の「おまけ」 |
||||||||||||||||||||||
| いかにもいかにもといえば、上の Nox Arcana に負けず劣らず笑えるほどいかにもいかにもなのが; Jacula, Tardo pede in magiam versus, 1972(邦題:ヤクラ『サバトの宴』)(5) 個人的に苦手な〈語り〉がいやに多いのが個人的には辛いところですが、ともあれ最後の曲が "In Old Castle"(「古城にて」)。 さいわい〈語り〉は無しで、パイプ・オルガンが10分弱鳴り響きます。 |
5. 『ユーロ・ロック集成』、マーキームーン社、1987/90、p.37。 『イタリアン・ロック集成 ユーロ・ロック集成1』、マーキームーン社、1993、p.66。 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.34、2007.8、p.13。 アウグスト・クローチェ、宮坂聖一訳、『イタリアン・プログ・ロック イタリアン・プログレッシヴ・ロック総合ガイド(1967年-1979年)』、マーキー・インコーポレイティド、2009、pp.287-288。 岩本晃一郎監修、『イタリアン・プログレッシヴ・ロック(100 MASTERPIECE ALBUMS VOL.1)』、日興企画、2011、p.94。 |
|||||||||||||||||||||
もう1作イタリアのプログレから; Osanna, Landscape of Life, 1974(邦題:オザンナ『人生の風景』)(6) |
6. 『イタリアン・ロック集成 ユーロ・ロック集成1』、マーキームーン社、1993、p.90。 アウグスト・クローチェ、宮坂聖一訳、『イタリアン・プログ・ロック イタリアン・プログレッシヴ・ロック総合ガイド(1967年-1979年)』、マーキー・インコーポレイティド、2009、pp.377-380。 別のアルバムから→こちらで挙げました;「グノーシス諸派など Ⅲ」の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
| メロトロンも大いに轟く名作の誉れ高い『パレポリ Palepoli 』(1973→そちらでも少し触れました:「インド」の頁の「おまけ」)に続く4作目で、その劈頭を飾るのが "Il Castlello dell'Es"(「城」)。 "Es"は手もとの伊和辞典によると 語頭が大文字で"einstenio"の略、 化学用語で元素アインスタニウム、 頭が小文字だとやはり"esempio"(「例」)、あるいは"esame"(「試験」)、さらに"esente"(「免除」)の略 とのことで、よくわかりませんでした。あるいはドイツ語の非人称の主語に由来する〈エス=イド〉のことでしょうか(→あちらを参照:「近代など(20世紀~ ) Ⅲ」の頁の「xv. 時間論、その他」)。歌詞はイタリア語なのでおぼつかないこと甚だしいのですが、歌詞カードでは 「エスの城では存在は不確かになる。 私は水、私は時、私は…私は火、 たぶん私はどれでもない」 と歌いだしているようです。前作に比べると評価の高くないアルバムではありますが、9分弱のこの曲は多少とも面影を残しているといえるでしょうか。 なおこの曲は Osanna & David Jackson, Prog Family, 2009 でも8曲目として演奏されています。 →ここ(ダニエレブスキー『紙葉の家』(2000)+モーゲンスターン『地下図書館の海』(2019) メモの頁)でも触れました。 古城といえば、ムソルグスキーの『展覧会の絵』にも入っています。"Il vecchio castello"とイタリア語で表記されるようですが、ともあれピアノ原曲やラヴェルによるオーケストラ版は数多あることでしょうが、ここではやはり; |
||||||||||||||||||||||
| Emerson, Lake & Palmer, Pictures at an Exhibition, 1971(邦題:エマーソン、レイク&パーマー『展覧会の絵』)(6-2) EL&P は組曲すべてを取りあげているわけではありませんが、「古い城」は入っています (→こちらでも触れています:『インフェルノ』(1980)の頁中)。 |
6-2. 松井巧、『エマーソン、レイク&パーマー』(地球音楽ライブラリー)、TOKYO FM 出版、1996、pp.22-23、。 『エマーソン・レイク&パーマー 文藝別冊 KAWADE夢ムック』、2016.7、pp.186-187。 円堂都司昭、『意味も知らずにプログレを語るなかれ』(Guitar magazine)、リットーミュージック、2019、pp.121-127。 |
|||||||||||||||||||||
| 冨田勲、『展覧会の絵』、1974 Mekong Delta, Pictures at an Exhibition, 1996(邦題:メコン・デルタ『展覧会の絵』) このアルバムはバンドとオーケストラ入りでそれぞれ全曲が演奏されています。なので「古い城」も2通り。オーケストラといっても、コンピューターによるサンプリングとのことで(日本版ライナーノート、pp.13-14)、エレクトリック・バンドとオーケストラが協演する時にありがちな肌合いの違和感はあまり感じられません。 →こちらも参照:「近代など(20世紀~ ) Ⅳ」の頁の「おまけ」 「古城」は出てきませんが『展覧会の絵』が核になっているのが; 石神茉莉、「音迷宮」、東雅夫編、『稲生モノノケ大全 陽之巻』、毎日新聞社、2005、pp.417-444 (再録:石神茉莉、『音迷宮』、講談社、2010、pp.3-36) 初出収録書のタイトルからうかがえるように、この短篇は『稲生物怪録』(→こちらも参照:「日本 Ⅱ」の頁の「vii. 国学など」)に想を得たものでもありました。『音迷宮』の単行本はページ見開きの左下、ページ表記のすぐ右に各短篇のタイトルが記されているのですが、短篇の終わりでのみ、語られる存在等の呼び名に代わっています。この短篇の場合は「稲生物怪録」とありました(p.35)。 ちなみに、『稲生物怪録』とのつながりは長篇 石神茉莉、『謝肉祭の王 玩具館綺譚』(講談社ノベルス イQ-02)、講談社、2009 冒頭のエピソードでも見ることができます。p.24 では『稲生物怪録』の名も挙げられていました。他方、『謝肉祭の王』での設定は、『音迷宮』所収の「Rusty Nail」(初出:2007)と共通しています。後者の終わり近くの見開き左下には「ポンティアナ」とあって(p.153)、これはマレーシアのポンティアナックのことかと思われます (ポンティアナックのイメージについて、とりあえず手もとにある、四方田犬彦、『怪奇映画天国アジア』、白水社、2009、pp.247-266 参照)。 またこの著者の作品にはしばしば音楽が小さからぬ役割を果たしますが、『謝肉祭の王』ではベルリオーズの『幻想交響曲』終楽章が挙げられていました(p.29 など)。 ついでに主要な舞台の一つ〈玩具館〉の店長Tはゾンビをこよなく愛しており、長篇第一作『人魚と提琴』(2008)ともどもゾンビ映画がしばしば言及されるのですが、本作ではあわせて、仮面のモティーフにからんでかの『血ぬられた墓標』(1960)のタイトルも挙がっています(p.33)。 それはともかく、『謝肉祭の王』や「Rusty Nail」は他方、やはりこの著者の作品にくりかえし登場する、胎児や赤子のイメージを扱うものでもありました。 同じ著者による→そちらを参照:「夢オチ禁止」、『人魚と提琴』他について/「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「xix. ラヴクラフトとクトゥルー神話など」 |
||||||||||||||||||||||
→こちら(「アメリカ大陸など」の頁の「おまけ」)で'castle in Spain'という成句について触れましたが、そう言えば Jimi Hendrix Experience, Axis : Bold as Love, 1967(邦題:ジミ・ヘンドリックス、『ボールド・アズ・ラヴ』)(7) |
7. 『文藝別冊 総特集 ジミ・ヘンドリックス』(KAWADE夢ムック)、河出書房新社、2004、p.147。 →そちらも参照:「アメリカ大陸など」の頁の「おまけ」の別の箇所 |
|||||||||||||||||||||
| のA面3曲目は"Spanish Castle Magic"(「スパニッシュ・キャッスル・マジック」)でした。このアルバムにはさらに、B面2曲目に"Castles Made of Sand"(「砂のお城」)が収められています。 | ||||||||||||||||||||||
Klaus Schulze, Irrlicht, 1972(邦題:クラウス・シュルツェ『イルリヒト(オーケストラとE.マシーンズの為の4次元的交響曲)』)(8) |
8. 『ジャーマン・ロック集成 ユーロ・ロック集成2』、マーキームーン社、1994、p.90。 | |||||||||||||||||||||
| のCDに収録されたボーナス・トラックが"Dungeon"(「地下牢」)でした。24分にわたって電気的な持続音(ドローンと呼んでいいのでしょうか?、中ほどで少し変化します)が空間の地平を形づくり、少し遠目でやはり電気的なぴょろろ~んといったソロだか音が鳴るといった曲です。 余談ですが「ダンジョン」の語はゲーム等ですっかりお馴染みになりましたが、仏語版ウィキペディアによると(→こちらを参照) 仏語の"donjon"は主塔、天守を意味し、また特に孤立させておくべき囚人のために用いられることもあったとのことです。 英語でも中世には〈主塔〉の意味でしたが、後にもっぱら地下牢を指すようになったという。 そのため日本語版ウィキペディアの「ダンジョン」(→そちら)から対応する仏語頁に飛ぶと、"donjon"ではなく"oubliette"が開くのでした(→あちら)。英語頁は"dungeon"です(→ここ)。 ジャン・メスキ、『ヨーロッパ古城物語』、2007、pp.116-121:「ドンジョン、あるいは最後の避難所」、および pp113-116:.「地下道、あるいは『城の謎』」「地下の城」 も参照. なお「ウブリエット」の語には『ラビリンス -魔王の迷宮-』(1986)でお目にかかりました(→こちらを参照:当該作品の頁)。 |
||||||||||||||||||||||
Hands, Hands, 1996(邦題:ハンズ『迷宮への道』)(8a) |
8a. 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.61。 →こちら(「アメリカ大陸など」の頁の「おまけ」)や、またそちら(「中央アジア、東アジア、東南アジア、オセアニアなど」の頁の「おまけ」)で別の曲を挙げています |
|||||||||||||||||||||
|
前身バンドの Prism 時代のこと、 「この時期、彼らにとって最高のできごとだったのは、ジェントル・ジャイアントのダラス公演のオープニング・アクトをつとめたことである。GG は彼らにとって最大のアイドルだった。GG 来訪の知らせを聞き、メンバーがただちにブッキング・オフィスに出向いて演奏権を獲得したという。このときの演奏と観客の反応は、彼らの全キャリア中最高のものだったとされている。演奏が終わるや、GG のメンバーが拍手喝采でステージに出てきたそうである」 (三輪岳志による日本版ライナー・ノーツ、pp.4-5。Rick Koster による英語版ライナー・ノーツの6ページ目も参照) という、聞く者によっては涙なしではいられない逸話を残すUSAのプログレ・バンド、しかし当時はアルバム制作にまでいたらず、1977~80年に録音された素材を後になって編集したCDの末尾、14曲目が"Castle Keep"です。ボーナス・トラックということで、日本版ライナー・ノーツのリストにも右の註のディスク・ガイドにも挙がっていないのでした(後者ではなぜか同じくボーナス・トラックの13曲目は載っている)。3分36秒、比較的景気がいい、歌入りハード・ロック調の曲です。なおバンドは後に再結成されたとのこと。 |
||||||||||||||||||||||
Leviathan, Leviathan, 1974(邦題:レヴィアサン、『レヴィアサン』) (→こちらも参照:「原初の巨人、原初の獣、龍とドラゴンその他」の頁の「おまけ」) A面ラスト、4曲目の"Endless Dream"(「果てなき夢」)のコーラスは、 "You will see a mystery castle floating in the air" というものでした。9分56秒。 Blue Öyster Cult, Imaginos, 1988 (→そちらも参照:「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「おまけ」) 元のLPならやはりA面ラスト、5曲目の"The Siege and Investiture of Baron von Frankenstein's Castle at Weisseria"、6分43秒。 ところでタイトルにある"Weisseria"は、『フランケンシュタインの幽霊』(1942)および『フランケンシュタインと狼男』(1943)の主要な舞台のひとつ"Vasaria"や『フランケンシュタインの館』(1944)での"Visaria"を連想させずにいません。何か関係があるのでしょうか? |
||||||||||||||||||||||
| 日本のバンドに戻ると; ジェラルド、『虚実の城 Empty Lie, Empty Dream 』、1985(8b) 2枚目のB面1曲目がタイトル曲。 |
8b. ヌメロ・ウエノ、たかみひろし、『ヒストリー・オブ・ジャップス・プログレッシヴ・ロック』、マーキームーン社、1994、pp.107-109。 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.155。 |
|||||||||||||||||||||
| ちなみにジャケットはジョン・エヴァレット・ミレーの《オフィーリア》(1851-52)でした。なので→こちら(ミレー《オフィーリア》の頁の「おまけ」)にも挙げてあります。 | ||||||||||||||||||||||
アウターリミッツ、『少年の不思議な角笛』、1986(9) B面2曲目が"Out of the Old Castle" |
9. ヌメロ・ウエノ、たかみひろし、『ヒストリー・オブ・ジャップス・プログレッシヴ・ロック』、マーキームーン社、1994、pp.50-53。 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.143。 →こちらもを参照(「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「おまけ」) |
|||||||||||||||||||||
ページェント、『螺鈿幻想』、1986(9a) 全体に怪奇趣味が漂うアルバムですが、B面ラスト、3曲目「エピローグ」(6分41秒)では、 「私ガ眠っていた お城に着くはず」 と歌われます。 |
9a. ヌメロ・ウエノ、たかみひろし、『ヒストリー・オブ・ジャップス・プログレッシヴ・ロック』、マーキームーン社、1994、pp.175-178。 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.169。 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.29、May 2006、pp.70-71。 『ストレンジ・デイズ』、no.82、2006.7、pp.133-136。 →こちらも参照:『ウルトラQ』第9話「クモ男爵」(1966)の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
フロマージュ、『オフェーリア』、1988/1994(10) の6曲目が「 |
10. ヌメロ・ウエノ、たかみひろし、『ヒストリー・オブ・ジャップス・プログレッシヴ・ロック』、マーキームーン社、1994、pp.173-174。 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.169。 →こちらでも挙げました(J.E.ミレー《オフィーリア》(1851-52)の頁の「おまけ」) |
|||||||||||||||||||||
| マージュリッチ、『悲劇の泉』、1995(11) 2枚組の内2枚目の4曲目が"Haunted Mansion" |
11. cf., ヌメロ・ウエノ、たかみひろし、『ヒストリー・オブ・ジャップス・プログレッシヴ・ロック』、マーキームーン社、1994、p.224。 | |||||||||||||||||||||
| ちなみに先立つ マージュリッチ、『真実の指輪』、1992 の3曲目は"The Haunted Woods"(「魔物の森」)でした。 |
||||||||||||||||||||||
美狂乱、『狂暴な音楽』、1997(12) 4曲目が「狂暴な砦」。 ちなみに本曲ではそうでもありませんが、アルバムの随所でメロトロン(らしき音)が前面に出ます。ところどころでマリンバもころころ転がります。 |
12. 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.169。 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.44、2010.2、p.164。 →こちらも参照:「アフリカ」の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
やはり日本のバンド Electric Asturias, Fractals, 2011(13) の3曲目が"Castle in the Mist"。器楽曲です。 |
13. 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.51、2011.11、p.23。 →こちらも参照(「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「おまけ」) |
|||||||||||||||||||||
カンタベリー・ロックの極北にしてチェンバー・ロックの流れに棹さすバンドの2枚目、 Henry Cow, Unrest, 1974(14) A面3曲目で後半を占めるのが"Ruins"、12分0秒、器楽曲。 この曲はライヴ・アルバム Henry Cow, Concerts, 1976(邦題:ヘンリー・カウ『コンサーツ』)(14a) にも収められています。LPとCDでは曲順が違うところがあるそうなのですが、とまれ手もとのCDでは DISK 1 の3曲目、16分14秒。 同じアルバムから→あちらを参照:「錬金術など」の頁の「おまけ」 |
14. 竹田賢一、「〝内容〟と〝形式〟を兼ね備えた真の前衛 - ヘンリー・カウ」、『ミュージック・マガジン』、no.143、1980.3、pp.96-101。 The Bible. rock magazine 04、ロックマガジン社、1981、p.37。 「迷宮の地形学 前編 Henry Cow Art Bears」、『フールズ・メイト』、vlo.16、1981.4、pp.23-27。また同、「国内盤レヴュー」、p.86。 大鷹俊一監修、『ヤング・パーソンズ・ガイド・トゥ・プログレッシヴ・ロック』、音楽之友社、1999、p.100。 『200CD プログレッシヴ・ロック』、立風書房、2001、p.138。 松井巧監修、『カンタベリー・ミュージック(Artists & Disc File Series Vol.5)』(ストレンジ・デイズ12月号増刊)、2004、p.165。 深見淳・松崎正秀監修、『UKプログレッシヴ・ロック メインストリーム・エディション~The Golden Era』(THE DIG presents Disc Guide Series #017)、シンコーミュージック、2004、p.139。 『オール・アバウト・チェンバー・ロック&アヴァンギャルド・ミュージック』、マーキー・インコーポレイティド株式会社、2014、p.21。 ベンジャミン・ピケット、須川宗純訳、『ヘンリー・カウ 世界とは問題である』、月曜社、2023、pp.168-169。 →こちら(北欧、ケルト、スラヴなど」の頁の「おまけ」)や、またそちらも(「インド」の頁の「おまけ」)も参照 14a. 前註で挙げたもの以外に; 松山晋也監修、『プログレのパースペクティヴ MUSIC MAGAZINE 増刊』、ミュージック・マガジン、2000、p.112。 |
|||||||||||||||||||||
スウェーデンのトラッド成分+ジャズ成分+お笑い成分入りプログレ・バンドの、ギターが加わった2枚目、 Samla Mammas Manna, Måltid, 1973(15) 8曲目が"Minareten"、8分21秒。ヴォーカルというか人声は入りますが、歌詞はないようです。手もとに詳しいスウェーデン語の辞書がないので、タイトルがイスラーム建築の塔〈ミナレット〉を意味するのかどうか、定かではないのですが、一応挙げておきます。 |
15. 片山伸監修、『ユーロ・プログレッシヴ・ロック The DIG Presents Disc Guide Series #018』、シンコーミュージック、2004、p.105。 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.36、2008.2、pp.82-85。 『オール・アバウト・チェンバー・ロック&アヴァンギャルド・ミュージック』、マーキー・インコーポレイティド株式会社、2014、pp.138-149。 →こちらも参照:「ユダヤ Ⅲ」の頁の「おまけ」、また→そちら(「アメリカ大陸など」の頁の「おまけ」 |
|||||||||||||||||||||
| また手もとにあるCDにはボーナス・トラックとして、10曲目に"Minareten II"が収録されています。4分37秒、やはり人声入り。間に当初のLPでは最後に位置していた9曲目がはさまっているのですが、8曲目の終わりの部分で消えていったベースのリフから始まるので、もとはいちどきに録音されたのかもしれません。 ちなみにミナレットにまつわる曲といえば→そちらも参照:「イスラーム Ⅲ」の頁の「おまけ」 |
||||||||||||||||||||||
Kansas, Masque, 1975 (邦題;カンサス、『仮面劇』)(16) 3枚目の8曲目、元のLPではB面最後の曲“The Pinnacle”(「尖塔」)、9分34秒。 |
16. 舩曳将仁監修、『トランスワールド・プログレッシヴ・ロック DISC GUIDE SERIES #039』、シンコーミュージック・エンターテイメント、2009、p.16。 →こちら(「エジプト」の頁の「おまけ」)も参照 |
|||||||||||||||||||||
| 古城に関わるものではありませんが; Morte Macabre, Symphonic Holocaust, 1998(邦題:モルト・マカブル『シンフォニック・ホロコースト』)(17) 全8曲中、ラストのタイトル曲以外はホラー映画のテーマ曲をアレンジしたもので、そのいずれでもメロトロンが大盤振舞されています。 |
17. 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.22、2004.8、p.63。 | |||||||||||||||||||||
| サムラ・ママス・マンナやモルト・マカブルと同じくスウェーデンのバンド; Anima Morte, The Nightmare Becomes Reality, 2011(18) |
18. 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.51、2011.11、p.76。 | |||||||||||||||||||||
| 2枚目で全11曲、すべて器楽曲なのですが、各曲のタイトルからしてホラー映画的なイメージのようです。メロトロンも鳴り響きます。曲名を並べておくと; "Voices from beyond" "Corridor of Blood" "The Revenant" "Contamination" "Passage of Darkness" "Solemn Graves" "Delirious" "Feast of Feralia" "The Nightmare Becomes Reality" "Things to Come" ”The Dead Will Walk the Earth" 8曲目の"Feralia"というのは英語版ウィキペディアによると(→こちら)、古代ローマのお盆のような祭りだそうです。 2曲目と5曲目は→そちらにも挙げておきます:「廊下など、メモ」の頁 「アンビエント~実験音楽シーン」(CDの帯より)と関連づけられるという 冥丁、『Kwaidan/怪談』、2018/2023 こちらも曲名を並べておくと; 「Sazanami/漣」 「Curio/骨董」 「Touba/塔婆」 「Jizo/地蔵」 「Aoyagi/青柳」 「Mōryō/魍魎」 「Sankai/山怪」 「Shoji/障子」 「Mushiro/筵」 「Tsukumo/九十九」 「Namida/涙」 「Kaikyō/海峡」 Kate Bush, Lionheart, 1978(邦題:ケイト・ブッシュ『ライオン・ハート』) セカンド・アルバムのB面ラストは"Hammer Horror"(「ハンマー・ホラー」) →こちらにも挙げておきます(『フランケンシュタインの逆襲』(1957)の頁の「おまけ」) →そちらも参照(「エジプト」の頁の「おまけ」) そこでハマー・フィルムの映画音楽集; Hammer. The Studio That Dripped Blood!, 2002 →こちらを参照:『吸血鬼ドラキュラ』(1958)の頁の「おまけ」 またハマーのものに限らず; Best Hits Horror Movie(邦題:『ベスト・ヒッツ・ホラー・ムービー』、2006) →こちらを参照:『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922)の頁の「おまけ」 Gryphon, Gryphon, 1973(邦題:グリフォン、『鷲頭、獅子胴の怪獣』) (→こちらを参照:「キリスト教(西欧中世)」の頁の「おまけ」) 1枚目の6曲目(元のLPではA面ラスト)は"The Unquiet Grave"(「無気味な墓場」)、5分40秒。 この曲はイギリスのトラディッショナル・フォーク・ソングです。 英語版ウィキペディアの該当頁(→そちら)によると、ある男性があまりに恋人の死を嘆くもので、恋人が現われて安らぎを得られないと告げるというものだそうです。なので'unquiet'というのは邦題にある「無気味」というより、文字どおり「静かでない」ことなのでしょう。 また同頁の"Recordings"の項には、グリフォンも含めて、スティーライ・スパン、スティーヴン・ウィルソン、ジョーン・バエズなどなどなど、この曲を取りあげた数多くの音楽家が挙げられています。 『オトラントの城』、1973-79、監督:ヤン・シュヴァンクマイエル、18分 (DVD『ヤン・シュヴァンクマイエル 「ジャヴァウォッキー」その他の短篇』所収) シュヴァンクマイエルに関連して→こちらも参照:「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「追補の2」 |
||||||||||||||||||||||
| ちなみに美術に関する旧拙稿で古城ネタに交わるものとして、「階段で怪談を」(<美術の話)以外に、前の職場のサイトに載せてもらっているものは; 「第2回具象絵画ビエンナーレより+ミニ用語解説《カプリッチオ》+館蔵品から/表紙/裏表紙解説」、『友の会だより』、no.15, 1987.7.10 [ < 三重県立美術館のサイト ] 「シャルル・メリヨン《プティ・ポン》(館蔵品から)」、『ひるういんど』、no.20、1987.8 [ < 同上] 『常設1995年度第3期』、1995.9、:■第1室:昭和前期の洋画 [ < 同上] 「シャルル・メリヨン《プチ・ポン》《ノートル=ダムの給水塔》《ノートル=ダム橋のアーチ》《塔・医学校通り》」、『コレクション万華鏡-8つの箱の7つの話』、1998.9 [ < 同上] 「プチ・ポン拾遺 - メリヨンとマティス - 研究ノート」、『ひるういんど』、no.69、2000.3 [ < 同上] 「マティスのノートル=ダムの塔の上 ─ プチ・ポン拾遺の拾遺 ─ (研究ノート)」、『ひるういんど』、no.70、2001.2 「前田寛治《風景》」、『友の会だより』、no.72、 2006.7.10 [ < 同上] 「シャルル・メリヨン《プチ・ポン》」:美術館のコレクション・パンフレット 2007年度第3期展示、2007.10.2 [ < 同上] 「出品目録+ガイド」、移動美術館 員弁コミュニティプラザ:『建物のある風景』、2008.11.12 [ < 同上] 次の2つはまあ…ということで; 「とくべつふろく」、 『子ども美術館Part2 こわいって何だろう?』ガイドブック、1997.7 [ < 同上] 「おすすめの美術館(2) ビリャファメース民衆現代美術館(スペイン)、他」、『学芸室だより』、2009.2.16 [ < 同上] 次の2つもまあまあ……ということで; 「いくつかの噂の顛末」、『HILL WIND』、no.2、2003.12 [ < 同上] 「初めての展覧会:幻の展観の巻」、『学芸室だより』、2005年12月(第6回) [ < 同上] 古城がらみというわけではありませんが、怪奇映画・怪奇小説に関わって; 「吸血鬼は十字架を恐れるか?-ビクトル・ミラ『神に酔いしれて』をめぐって(上) - 『100の絵画・スペイン20世紀の美術』展より -」、『ひるういんど』、no.37、1992.1 [ < 同上] 「吸血鬼は十字架を恐れるか?ビクトル・ミラ『神に酔いしれて』をめぐって(下) - 『100の絵画・スペイン20世紀の美術』展より -」、『ひるういんど』、no.46、1994.4 [ < 同上] |
||||||||||||||||||||||
| 2014/08/05 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||
| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城の外濠 > 怪奇城の外壕 Ⅱ > 怪奇城の外濠 Ⅲ |