| [10]<[9]<[8]<[7]<[6]<[5]<[4]<[3]<[2]<『ギュスターヴ・モロー研究序説』(1985) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5.抽象 i. 先抽象をめぐる議論 『オルフェウスの苦しみ』(図250)はモローの友人で蒐集家のアントニー・ルーが所蔵していたもので、モローがそのアトリエから出した作品としては、最も仕上げられた状態から遠い位置にあるものである。画面はかなり暗いが、厚い塗りで絵具を画布にこびりつかせるようにして、風景を描いている。月は絵具をこねて盛ったようなマティエールを示している。画面の右下に、地面に伏しているオルフェウスの裸身が見える。彼のからだも細かく描き込まれているわけではないが、頭、腕、腰などは区別されている。背景の山は、『エウリュディケの墓のオルフェウス』(図239→こちら)の場合とは逆に、赤の地の上に黒に近い濃褐色を塗ってある。画面の殆んどが形をなさないマティエールによって覆われているにもかかわらず、オルフェウスと月の小さな、はっきりそれとわかる形が描かれていることによって、この画面ははっきりした主題と、それに合致した感情を見る者に伝えることになる。ここでの暗い山とその上にかかる満月の組み合わせは、エルンストの『都市の全景』や『大いなる森』、あるいはセーヘルスの『谷間の川と滝』(これは月を描いたものではなく、刷りの時の処理の過程で、残ってしまったものらしい(386))を思い起こさせる。 図251 はさらに粗い状態で残されているもので、画面下の黒い部分、その上の褐色を基調にした部分、そして画面上の明るい部分は空であって、何かの風景を描いてあることはわかるが、細部を見きわめることはできない。筆致は、『オルフェウスの苦しみ』のように、絵具を稠密に画布に満たしていくものではなく、より幅広い、絵具の材質を強く感じさせるものである。 |
 図250 《オルフェウスの苦しみ》 1891頃、PLM.394 386. J.Rowlands, Hercules Segers, Paris, 1979, p.29.  図251 《エボーシュ》 MGM.  図252 《ナイルに流されたモーゼ》 1878、PLM.172 * 下の→こちらで触れています |
|||||||||||||||||||||||||||
| このような一見何が描かれているのかわからない画布がモロー美術館には少なからず残されており、1960年前後からの、モロー再評価の動きに大きな役割りを果たすことになった。モローの<抽象画>の問題に関しては、最近スーザン・フロイデンハイムが一篇の論文をまとめたが(387)、主な論点は1965年のホルテンの著作のこの問題を扱った箇所で、既に出尽くしていると言っても過言ではない(388)。 | 387. Freudenheim, ibid. 388. Holten, ibid., 1965, pp.170-175. |
|||||||||||||||||||||||||||
| モローを非具象絵画の先駆者とする見解は、1955年のイタロ・クレモーナのエッセイに始まって、1960年パリの装飾美術館で開かれた『アンタゴニスム』展、1961年ニューヨークの近代美術館の『ルドン、モロー、ブレスダン』展、1964年バーデンバーデンで開かれたモロー展などで大きく取り上げられた。1961年に書かれたポール・ジェンキンスのエッセイ(389)を除いて、これらの議論を見ることのできなかったのは残念だが、ホルテンやフロイデンハイムの引用によると、それは大凡次のようなものである
- クレモーナは、モローの絵の現代性に驚き、モローがそれまで描いてきた神話的寓意的構図から、晩年に至って自発的な色彩スケッチを制作するようになったとし、これを1950年代のタシスム、非具象絵画の先駆とみなす(390)。『アンタゴニスム』展のカタログに文章を寄せたジュリアン・アルヴァールは、ホルテンによれば「賢明で節度ある表現」(391)を示しているが、フロイデンハイムは「彼がはじめて、三つの重要な点とともに議論をひき起こした」(392)とする。即ち、「直ちにそれは先駆者ではない、と言おう。この度は問題はそこにはない。もし彼が抽象絵画を作ったとしても、それはうっかりしてである。即ち、三つの観察が重要となる:彼が |
389. P.Jenkins, "Gustave Moreau : Moot grandfather of abstraction",
Art News, 1961.12. 390. Holten, ibid., p.171. G.Schiff, "Die seltsame Welt des Gustave Moreau", Du-Atlantis, 1965.5, p.332. 391. Holten, ibid., p.171. 392. Freudenheim, ibid., p.72. 393. Holten, ibid., p.174 註 10. 394. id., 註 11. |
|||||||||||||||||||||||||||
| アルヴァールの節度に対して、1961年のルーヴルでのモロー展について書かれたミシェル・ラゴンの文章は、劇的な修辞をこととして科学的適切さに欠ける、とホルテンは言う(395)。より重要なのは、61年の『ルドン、モロー、ブレスダン』展のカタログに寄せられた、ドア・アシュトンの議論である(396)、「後年の主題画から小品の水彩油彩への移行は難しいことではない、それらの作品においては、見定めることのできる主題は何ら存在しないか、あるいは存在していてもあまりに曖昧なので、抽象に境を接している。そのような作品が200点前後残されており、その意味について激しく議論が戦わされた。何人かの批評家たちは、それらは単に、より大きな画面に<移す>ための、試みの習作にすぎないと主張した。また別の者たちは、モロー自身まじめに考えたわけではない、<未完>の着想であると考えた。モローがそれらに額をつけ、裏打ちするほどに、それらをまじめに考えていたという事実は残っている。それらには年記は記されていないが、技法の自由さから見て、晩年に属するものと思われる。晩年にモローは、彼は秘密好きな人間で、その烈しい内面の生活は注意深く隠されていたが、彼を強いて止まない冒険に乗り出したのである、そこでは彼自身でさえ、その『過剰なまでの批判力』をもってしても、すぐにその意味を見出すことはできなかった。人が彼に絵画の衰退について語る時、リュップはモローが次のように答えたと伝えている、『それが終わったと彼らは言う。始まったばかりなのだ』。ある意味でこれら諸元素、純粋な光の効果、雲、水の奔流の解釈は、モロー一人が考えていたことではなく、19世紀の画家たちや詩人たちが言い表わしたことの内に、ばらばらに姿を現わしていた思考であった … 誰が、これら油彩の小品を見て、<抽象的な>色と運動の体験が、モローを完全に引き込んでいたことを否定できよう?ある作品では、燃え上がる赤の形-薔薇かそれとも人物?-が、芸術家の指によって、マティエールから引き出されている。親指の指紋がはっきり見える …」。また『死せる竪琴』の水彩(図343→こちら)について、「その生涯の最後にモローが、『死せる竪琴』におけるように、その野心的な主題を総括しようとした時においてさえ、<観念>は後退し、手の衝動と線と色の詩が取って代わる」(397)。同じ主題の「油彩を描いた時、それは未完成に見えるけれども、芸術家を満足させたのであろう、モローは切れ切れの技法を繰り越した」(398)。 | 395. id., pp.171-172. 396. id., p.175 註 14. 397. id., p.99 註 31. 398. id., 註 32. |
|||||||||||||||||||||||||||
| ジェンキンスは、モローの意図が何であれ、これらの神秘的な作品は関心をひくものであり、原因が何であれ、それらが結果なのだと言い、ヴォルスやスティルの作品を思い起こしている(399)。1964年のバーデンバーデンのモロー展のカタログでディーター・マーロウは、「モローは当然、意識して非具象に描いたのではなかった」と言い、それらの概念は後に別の状況のもとに成立したものだと言うが、彼の風景習作は、「活気に満ちたタシスム的色彩構図である。そこでも何らかの、色彩の象徴的形態が求められているのを認めることはできるが、また描くことの歓びが、あらゆる奉仕から解放されて、己れ自身の内にその力を求めている」(400)。最近ではマテューが、モローに関与する大きな研究を著わした者の中では珍しく、その限界を認めながらも、これらの作品を積極的に評価し、カンディンスキーの歩みと比較している(401)。 | 399. Jenkins, ibid., pp.47-48. 400. Hofstätter, ibid., p.11. 401. Mathieu, "Gustave Moreau, premier abstrait?", Connaissance des Arts, 1980.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
| このようなモローの<抽象画>を非具象絵画の先駆と見なそうとする考えに対して、ホルテンはまず、クレモーナ以後一般に仮定されている、これらの抽象習作が晩年のものであるとする考えを、誤った一般化であるとする(402)。フロイデンハイムも同じく、このような習作は以前から制作されていたものと見なしている(403)。これらの作品に与えられている額は、モローによるものか、モロー美術館の実質上の設立者であるアンリ・リュップによるものか定かではない(404)。マテューはリュップによるものと述べている(405)。ただしそう述べたマテューが、これらの画布は板であれカルトンであれ、注意深く準備されており、その表面が完全に覆われているとして記していることに、注目しよう(406)。これらの作品の内には、署名を書き入れられているものがあるが、これはモロー美術館の構想を抱いた時点で、多くの素描に後から署名していることを考えねばならない。個人美術館というものは、モローの遺言によれば、「芸術家の、その一生の仕事と努力の総計を、認めることを常に許すような、全体としての性格を保つ」(407)べきもので、個々の作品を集めたものというよりは、「一つの綜合作品」(408)であるとホーフシュテッターは言う。画面に見える指紋の跡については、ホルテンはそれは彫刻に見えるのと同じで、重要ではないとする(409)。 | 402. Holten, ibid., p.171. 403. Freudenheim, ibid., p.74. 404. Holten ibid., p.172. 405. Mathieu, ibid., 1976, p.186. 406. id., 1980, p.88. 407. MGM.p.5. 408. Hofstätter, ibid., p.151, Holten ibid., p.172. 409. Holten, ibid., p.172. |
|||||||||||||||||||||||||||
| モローが自らの成果について意識していたことを論ずる際の支持として、本論文 106 頁以下に引用した文章(→こちら)や、自分のために制作する時のみ幸せなのだという発言とともに、次の文章が引かれることがある(410)、 | 410. Freudenheim, ibid., p.75. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 「ある事柄が私の内で大きな力を持っている、抽象化への大いなる牽引と熱情である。人間的感情、人間の情熱は確かにとても興味深いものだ;しかし私は、こういった魂と心の動きを表現すること以上に、いわば内なる閃光を目に見えるようにすることに惹かれる、それは何に関係づければよいのかもわからないものだが、見かけの無意味さの内に何か神的なものを有しており、純粋な造形の驚くべき効果によって表わされると、真に魔術的な地平を開くのだ、至高なと言ってもよかろう」。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| しかしここでの<抽象>という言葉は、ベルナール、ゴーギャン、ゴッホ等19世紀後半の反写実主義的、観念主義的芸術家たち一般に用いられていたもので (411)、今日言う<抽象>が第一に非対象であることを指すのに対し、19世紀の用法で問題になっていたのは、主題、絵に表わされるべき思想のことであって、これはモローでも同じである。ただゴーギャンらにおいても、<抽象>の問題は造形的処理と結びつきを示しているが、モローにおいても「純粋な造形」という言葉が示すように、20世紀において完全に承認されるようになる、造形至上主義への傾向を窺わせるような発言は、『チェチーリア』(図214→こちら)について説明は必要ないと語っていたことが示すように(→こちら)、少なくはなく、モローに常に見られる矛盾と動揺を示している。 | 411. 二見史郎『抽象の形成』紀伊國屋書店、1970、pp.22-24、30. 412. Holten ibid., p.159 註 13. 413. Paladilhe, Pierre, ibid., p.32. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 「構想において、芸術家のもとで精神と良識の合理的な結合が、殆んど純粋に造形的な想像的着想、即ち<アラベスクの愛>に取って代わる日、芸術は死ぬ」(412)。 「…線、アラベスク、造形的な諸手段による思考の喚起、そこに私の目的がある」(413)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、ホルテンは<抽象>作品の価値はモロー自身にとっても未知であったと言うものの(414)、基本的にはこれらの作品を、さらに進められるべき制作過程の一段階と見なし、それ以上の独立の意味を持つとか、モローがその<現代的>意義を意識していたということは認められず、この点で多くの評者と一致する(415)。ゲルト・シッフは、「彼はその油彩及び水彩習作の中で、私的な<コード>を展開させたのであり、それは彼に、一見最も自由な色彩即興の内に、未来の具象的構図を見分けることを許したのである」と述べている(416)。フロイデンハイムも、一見抽象的な画面と具象的な構図の「比較の作業を時と労力をかけて続けていけば、多かれ少なかれ、全てを読み解くことができるだろう」と考える(
417)。さらにモローに限らず、ターナー、ユゴー、アンソールなどの作品が抽象の先駆として取り上げられたことを、抒情的抽象あるいは抽象表現主義が承認され、その歴史的な評価の作業の一産物と見なしている(418)。 |
414. Holten, ibid., pp.172-173. 415. Pierre, ibid., pp.162-163. Kaplan, ibid., 1974, p.50. Hofstätter,ibid., pp.160-162. Hahlbrock, ibid., p.157. 416. Schiff, ibid., p.389. 417. Freudenheim, ibid., p.74. 418. id., p.71, 75-76. |
|||||||||||||||||||||||||||
| ii. <抽象画>の分類 例えば、先に見た 図251 は明らかに、1878年の万国博覧会に出品された『ナイルに流されたモーゼ』(図252)のための習作である。似たような画面で、スフィンクスの翼を見分けることのできる作品も先に見た(図57→こちら)。現在残されている事実から判断する限り、ホルテンやフロイデンハイムの主張の方に理がある。にもかかわらず、それは当然認めていなければならない前提にすぎない。19世紀の絵画が20世紀のそれと違うことは、どんなに類似した外見を示していても、当然のことである。むしろなぜ、19世紀の文脈の中でこのような結果が生まれたのか、モローの制作の内でどのような位置にあるのか、考えなければならないだろう。これらの問題については、既に何度も述べてきたので、ここで繰り返すことはしない。即ち、ルネサンス以来の、そして19世紀に頂点に達した、完成作の領域と習作の領域の分裂、モローにおける線の領域と色彩の領域の分裂、手、画家としての本能と理性、絵画に思想を担わせようとする意志との分裂、などがそれである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| マテューが引用する文章の中で、レオンス・ベネディットは、モローがその夢想を実現する過程に二つあるとして、第一が主題が与えるものから出発するのに対して、「またある時は、逆の方法によって、彼はその想像力を、色調の呼びかけによってかき立てる、その暗示力のある組み合わせは、彼の創造者としてすぐれて感受性の強い脳髄の中に、直ちに豊かな象徴の具体的な姿のもとに姿を現わす、感覚を目覚めさせる。ここではそれ故、働きかけるのは芸術の魔術であり、力を及ぼすのは色彩の神秘なのである。彼のアトリエにある、見かけは何が描いてあるのかわからない、幾つかの略画を見ればわかるように、パレットの上で偶然近づけられた、あるいは画布の上に並べられた何らかの色調だけで、彼がこの対比あるいは調和の中から、ある固有の言語の表現力豊かな意味を捉えるには充分なのである。彼は注意深く、これら自発的なあるいは思いがけない記号法を取り集め、それらが呼び起こす感情の内で、それらを完全なものにし、その明晰な目で、ゆっくりと彼の夢の形が浮かび上がってくるのを見つめる、ちょうど夜、金や紫水晶、黄金の円が私たちの閉じた目の影の中で、混ざり合って少しずつ、それらが生み出す印象のもとに花咲いて、夢の形が浮かび上がってくるように」と述べている(419)。マテューはこの文章を、アンリ・リュップの助言のもとに書かれたと考えている(420)。ハールブロックが指摘するように(421)、このような制作法は既にレオナルドによって報告されている。即ち壁のしみをじっと見つめていれば、そこに様々な具体的な形を見つけ出せるというものである(ただしレオナルドはボッティチェルリに反論して、それを絵画にまで仕上げる腕が必要だとも述べている)(422)。ハムレットとポローニアスの雲を見ての問答を思い起こすこともできよう。同様の観察はヘレニズム期にも、中国にも見出される(423)。アレクサンダー・カズンズはそれを、『風景画の独創的な構想を描く際の創意を助ける新しい方法』にまで高めた(424)。20世紀には、エルンストの<フロッタージュ>がある。モローは語る、 | 419. L.Bénédite, "Deux idéalistes, Gustave Moreau
et E.Burn-Jones", La Revue de l'art ancien et moderne, 1899.4.10, p.285. 420. Mathieu, ibid., 1984, p.110. 421. Hahlbrock, ibid., p.186. 422. Gombrich, ibid., pp.159-160. 423. id., pp.154-155, 158. 424. id., pp.155-158. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 「色彩を思考し、その想像力を持たねばならない。想像力を持たないならば、 決して美しい色彩は生じないだろう。…(中略)…色彩は考えられ、夢見られ、 想像されねばならぬ…」(425)。 またマテューは、モローの<抽象画>が完成作のための準備段階であることを示すものとして、モローのノートから次の文章を引用している(426)、 |
425. Michel 編, ibid., p.392. 426. Mathieu, ibid., 1980, p.88. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 「一点の作品にとりかかる前に、色価と彩色の調性をよく定めておくこと。一点の絵の彩色を徐々に減らして、最大限で二つか三つの色しか持たないようにし、主調となるものを決定すること。あらゆる調和を単彩にまで減らすこと(力強く、色は多様に)。絵を逆さにして、色価を確かめること、主題や描かれた対象、絵のありさまはあなたの目をそらしてしまうだろう」。 次になさねばならないのは、<抽象画>そのものに即して、その性格を見、分類することである。これらの作品を全て見たわけではないので、完全なものとはとても言えないが、手にすることのできた図版から見てとることのできる範囲内で、ごく簡単な分類を試みよう。 まず第一は、何らかの意味で風景が描かれていることを見てとることのできる作品がある。『勝利のスフィンクスのいる風景』(図57→こちら)でも、スフィンクスの翼のあるなしは別にしても、上に空のある、褐色のトーンで描かれた、モローが好んで描く荒涼とした岩山であることは、少なくともモローの他の作品を知っていれば、見てとることはできる。『捨てられたモーゼ』のための習作(図251)でも、事情は同じである。ここで描かれているべきなのは実は建築なのだが、モローにおいて建築も風景も本質的には違いがないことは、その大地的性格からしてあきらかである。図274(→こちら) は、風景と見るには無理があるが、青の部分は空、灰褐色の部分は地面と見ることができ、高く塔のようなものが聳え立っているらしい。 これらの作品に共通しているのは、そこに描かれている空間が広いものである、という印象を与えることで、それに伴って、筆触は広く大まかで、粗く画面全体に及ぼされ、絵はかすれたような表面を示し、一つ一つの色が強調されることなく、モノトーンに近いものになる、上下の区別がはっきりつくことなどがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 図253 も絵肌の印象はこれに近いものであるが、筆致はさらに粗々しく、白の部分の塗りも厚い。ここで絵の上下の区別がつくのは、天と地が描かれているからではなく、中央やや右寄りの赤の垂直軸と、それを取り巻く紺の太く長い、粗々しい曲線が、はっきり人間であることがわかるからである。それ故空間は狭くなる。全体の色調は未だ単彩に近いが、赤や紺などの色がはっきり独立し、白のマティエールも輝きが強い。 図254 では赤、黄がはっきりした、大きな塊まりになっている。空間はやはり狭く、モローの他の作品を知っていれば、描かれているのがおそらく室内で、右側の上で開いている、黒に近い濃紺の太い垂直の帯が柱であり、凍りつくような白が屋外を表わしているのだろうと見当がつく。赤の塊まりと黄の塊まりは、それぞれ人物であろう。今までの作例に比べて、塗りは稠密で、絵肌にはさほど粗々しい筆の痕跡は残されていない。モローがより仕上げられた作品で室内を描くとして、このような黒に近い暗さ、これに対して屋外の凍てつくような明るさを置くということは考えられず、こんなに大きな赤の塊まりの人物を描くこともない。これが細かく段階づけられて作品が完成する、と言うならそれはその通りなのだが、少なくともこの画面では、賦彩は色彩自身の論理に従って組み立てられていることを注意しておこう。 これは図255 ではさらに明瞭である。図254 でも赤や黄が、一種の<記号>的とも言うべき印象を与えていたが、ここでも赤、青、黄、薄目の緑が一つ一つ、独自の生命を持って動いているかのような、塊まりになっている。ここでは図254 以上に、それぞれの色を何らかの対象として考えることは難しく、一つ一つの色の塊まりも背景の筆触の動きも、今現在あるような状態以外のものとして画面を考えることは無意味である。この画面はあきらかに、これだけで<でき上がった>ものなのである。 |
 図253 《エボーシュ》 MGM.1135  図254 《エボーシュ》 MGM.1141  図255 《エボーシュ》 MGM.1139 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 第二のグループの作品では、色は一つ一つ分かれて大きな塊まりとなるが、それは未だ何らかの記号として、それが動くことのできる上下左右のある空間の中に配されている。これに対して次のグループの作品においては、そのような空間の暗示は消え、平面としての画布の表面への意識が支配的となる。それ故第一のグループにおけるように、筆致はある記号の上に凝集するのではなく、画面全体に分散されることになるが、一つ一つの色は独立し、もはやいかなる対象の痕跡も認めることはできず、色の動きは荒れ狂うようになり、マティエールに対する意識が強くなる。図256
はそうしたものの一つで、色彩を絵具のチューブを直接画布になすりつけたものらしい。濃紺の部分が下であろうことはわかるが、奥行きのイリュージョンは全く感じられず、表面に対する意識が支配的で、絵具の塗られていない部分も少なくない。色彩の方向は皆上昇しようとする動きを示しているが、マティエールの稠密さが、絵具をその場に凝固したように見せている。この動きが全て垂直に配されていることは、画面の枠に対する意識が働いていることを感じさせる。フロイデンハイムはこの作品を『ヒュドラ』(図6→こちら)のための習作と考え、「作品の中央では、三つの暗緑色の垂直の筆致が、高さを変えながら配されて、赤みがかった茶の背景に対して大胆に立ち現われている。同様に、暗緑色のヒュドラが完成作では、様々な高さの頭で、土色の調子の背景に対して並べられている」(427)。その気になればそう見えないこともないが、この指摘がこのような画面に対してどれほど意味を持つのか、甚だ疑わしい。 図256b では筆致はもう少し細かく、白い部分の明るさを天と見なすことができるが、両側、最上部にも暗い部分があるので、絵の上下に確信を抱かせない。先の丸くなった筆致を示すものが多く、アシュトンが指で描いたというのは、こういうもののことであろう。 図257 ではさらに上下の判別がなし難い。このような作品に対して、これを完成作品のための準備過程の一段階として片付けることは殆んど意味がなく、その点ではここに非具象絵画の先駆を見た論者たちの方が、むしろ絵に即して語っているのである。そしてこのような画面と念入りに仕上げられ、象徴的な思考を担わされた画面との落差の中にこそ、モローという画家の本質が隠されていると言うことができる。 |
 図256 《エボーシュ》 MGM.1151 427. Freudenheim, ibid., p.74. 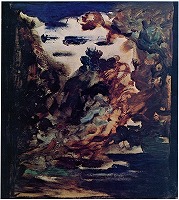 図256b 《エボーシュ》 MGM.1153  図257 《エボーシュ》 MGM. |
|||||||||||||||||||||||||||
| いわゆる抽象絵画の成立以前に、非具象的な画面を残した画家は、必ずしも稀有というわけではなく、完成作で精緻な仕上げを示している画家でも、習作類の中に何が描かれているのかわからない画面が見出される可能性がある。また印象派の<もやのかかった>ような作品にも、そうした例を見出せるであろうことは、松方コレクションにあるルノワールの『木かげ』が示唆している。抽象への動きは19世紀全体の趨勢だったのである。こうした流れの中で、最も組織的にこうした動きを反映している画家としては、モロー以外に、ターナー(→たとえばこちら)、ホイッスラー、モネなどが挙げられる。このいずれもヴェネツィアとロンドンに深い関わりを持つ三人の画家は、それぞれ性格を異にするものの、風景画の中で対象を稀薄に拡散させていくことによって、抽象に近い画面を残し、それ故その色調はしばしばモノトーンに近づく。これに比べるとモローは、抽象習作においてもより仕上げられた作品と同様に、マティエールを凝集させる大地的性格を示す。上の三人の中ではターナーが最もマティエールを拡散させること多く、これは油彩以上に彼の水彩において著しい。その大気的な性格においてはモローの対極にいるターナーも、その歩みの中で色彩に非現実的な輝きを与えていったことは、ターナーの作品がモローを忘我の状態に陥らしめたことを伝えるエドモン・ド・ゴンクールが、その作品に対して、モローの作品にも与えることができそうな「宝石の神化」という言葉を用いていることに示されている(428)。三人の中では、そのマティエールや色彩において、モネが最もモローに近いが(429)、彼の空間の性質はモローのそれと全く異なっている。バシュラールが引くドールスの言葉が示すように(430)、モネの空間はターナーとも違い、言うならば彼には水への牽引が強い。またモローにおいても、溶岩の流れのような図256、図257 やより仕上げられた作品の宝石の輝きには、大地に火の要素が混じっている。 モローの最も抽象的な画面が殆んど油彩にあることは、その大地性とともに、それがより密接に完成作に向けての過程の中に位置づけられていることを示している。これらの画面は、制作の最も初期の段階にではなく、多少とも構図の骨組みができ上がってからのものであるということも考えられる。 |
428. E. et J. de Goncourt, Journal 1889-1891, Paris, p.211, 及び Mathieu, ibid., 1984, p.104. 429. cf. Boime, ibid., p.160. 430. バシュラール『水と夢』小浜俊郎他訳、国文社、1969, p.49. |
|||||||||||||||||||||||||||
| しかし水彩画にも、油彩ほどではないにしても、非具象性の進んでいる作品も皆無というわけではない。これまで見てきた例の中では、『旅人オイディプス』の水彩(図50→こちら)がそうした傾向の強いものとして挙げることができ、素描でも『ヒュドラ』のための素描の一枚(図11→こちら)を同じ分類に加えることもできる。 『水浴する女』(図258)では黒、青、赤、緑などがはっきり分離され、女の輪郭が描かれていなければ、何が描かれているのかわからないだろう。ただここでは、モローが最も自由な作品でも常に心にかけていた、色調の統一はまだ達成されていない。 『聖アントニウスの誘惑』(図259)では画面は褐色を中心にして色班の乱舞である。よく見ると細い線が描き込まれており、聖人や山羊、右側の蛇や巨大な首、左端の背の高い女などを見分けることができる。なおこの主題はモローには珍しい。 『ケンタウロスの戦い』(図260)では地の白がかなり残っている。ここでも褐色が主だが、色面としてよりは太い線として用いられて、粗々しく動いている。題名を聞くことによって争うケンタウロスたちの姿を見分けることができる。ケンタウロスという自然の精霊の戦いに託される内容と、モローの筆致の激しさが一つになっている。右側にも女の姿が描き込まれている。 図261 は水彩において、全く対象を見分けることのできない作品の例である。画面の上下も必ずしも定かではない。しかし画面の枠に対する意識は、枠に沿って水平垂直に流された絵具の動きに現われている。この水彩には、鉛筆による線も縦横に走っているが、そこからも対象を読みとることはできない。 |
 図258 《水浴する女》 MGM.578  図259 《聖アントニウスの誘惑》 MGM.525  図260 《ケンタウロスの戦い》 MGM.386  図261 《エボーシュ》 MGM.490 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6.眼のない顔 i. ヘレネー:エボーシュ、スカイア門のヘレネー モローの抽象画は、モロー美術館のカタログでは皆< |
431. この語については、Boime, ibid., p.81.  図262 《エボーシュ》 MGM.903 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 『スカイア門のヘレネー』(図263)もヘレネーの主題を取り上げたものだが、1880年のサロン出品作とは構図が変わっており、マテューはこの作品を、1976年の著作では1880年頃としているが(432)、1984年のモロー展のカタログでは1890年頃に下げている(433)。この作品には同じ構図の素描があり、油彩の右の扉の前の濃褐色のしみの集まりが、女たちであることがわかる。彼女たちは棕櫚の葉を持って坐り、左の方を見ている。そこにはやはり人物のグループがざっと描かれている。この素描には、「ヘレネーが城壁の上を通る。トロイアの女たちは、死せる戦士たちの屍を守る」と書き記されている(434)。 城壁の扉口の位置は、『エウリュディケの墓のオルフェウス』(図239→こちら)の墓所とほぼ一致する。この作品で最も目を魅くのは、画面を大きく占める白い壁である。これはドラクロワの『ユダヤの結婚式』(図63→こちら)や『メクネスの通り』を思い起こさせるが、また『神秘の花』(図171→こちら)や『アルゴナウタイの帰還』(図173→こちら)の画面の明るさとも関連させることができる。あの二点の作品で衰耄を感じさせたものはしかし、ここでは一切の細部を省かれることによって、画面の強固さとなっている。色調は白と濃褐色で構成され、点々とばらまかれた黄と赤が両者の間を仲介している。空は灰色のべた塗りで、壁の白さを強調している。壁の白は微妙に灰色と混ぜられており、これが壁の表面に緊張感を与え、表面のマティエールの強固さを感じさせる。これに応じて、ヘレネーの姿もサロン出品作のそれに比べて、縦長に引き延ばされ、細部を除かれ、丸みを帯びた単純化された肉付けは、 この作品において、画面全体の大胆な配色に対してヘレネーの姿を耐えさせているのは、形態の単純化とともに、先の『エボーシュ』同様顔に目鼻立ちが描かれていないことによる。もし顔の造作が描き込まれていたら、彼女の姿はもっと弱さを見せるものになっていただろう。眼と視線のモティーフの強調が、ある意味で造形的な弱さと裏表であることは既に触れたが、ここで眼の無いことは単に造形的な問題に留まらず、描かれた対象の非人間的な強靭さをも暗示している。それを強調するのは、80年のサロン出品作からさらに純化された、その柱のような形態で、この顔の無いヘレネーは確かにキリコを思い起こさせるが(436)、キリコのマネキンたちより単純に、己が居場所で自足している。 |
 図263 《スカイア門のヘレネー》 MGM.42 432. Mathieu, ibid., 1976, p.143. 433. 『モローと象徴主義の画家たち』, ibid., p.122. 434. MGMd.131. 435. Mathieu, ibid.,1976, p.142. 436. 竹本忠雄『モロー』新潮美術文庫、1975、図18解説. |
|||||||||||||||||||||||||||
| ii. 栄光のヘレネー、贖い主キリスト 美術学校のモローの教室に学んでいたアンリ・エヴヌポワルが、ある日モローのもとに自分が描いたポーの挿し絵を見せに持って行った時、モローは、あなたはこういった方面には向いていない、ルドンは優しく良い奴だが結果は悲しむべきものだと言って、エヴヌポワルにこうした分野の危険を説く中で、「どんな種類でも屍や、解体、腐敗、恐怖などを表わす姿から離れなさい」と勧めている( 437)。この会話を報告しているエヴヌポワルの手紙は1894年4月21日付けのもので、ホルテンはモローが、以前の『ヒュドラ』(図6→こちら)のような作品でしばしば、打ち壊された屍の血の滴る山の見本を示したにもかかわらず、晩年にはそのような、気味の悪い主題の領域からは身を引いた、と述べている(438)。しかしこの会話の行なわれる 4、5年前に、モローは『神秘の花』(図171→こちら)を制作しているし、同じ頃文字通り屍の陳列場である『求婚者たち』(MGM.19)の制作も再開していた。 『神秘の花』の構想がヘレネーの図像及びその内容と関連を持っており、そこにおいて聖母マリアが<宿命の女>の神格化の例となったことは、先に見た通りである(→こちら)。同じ変貌は、ヘレネーからマリアへの移行において起こっただけではなく、最晩年ヘレネー自身の上にも生じた。これを示すのが『栄光のヘレネー』の図像である。 |
437. Michel 編、ibid., pp.397-398. 438. Holten, ibid., 1965, p.161. |
|||||||||||||||||||||||||||
| モロー美術館にあるこの主題の水彩画(図264)には、1897年の年記が記されている(訂正:1887年の誤り)。濃紺を背景に、正面を向いたヘレネーが老若四人の男たちを従えて、宙に浮いている。彼女は巨大な光輪をつけ、画面下方にも幾つもの光を発する球体が浮いている。四人の男は老王、詩人、戦士の三人とアモールで、三人は現在所在不明の『洞窟のスフィンクス、詩人、王そして戦士』(PLM.415)及び『旅人オイディプス』(図48→こちら)に現われ、人類を代表しているであろうことは、既に述べた(p.104→こちら)。アモールは一年前に描かれた『ユピテルとセメレー』(図268→こちら)にも登場していた。そこでは山羊の脚をした「地上の愛の精」と呼ばれており、これは『レダ』の解説にも現われていたが(→こちら)、さらには1856年に死んだシャセリオーを讃えるために構想され、65年のサロンに出品された『若者と死』(PLM.67)の中で、若者の足もとで消えかけた松明を掲げている有翼の童子にまで遡ることができる。この子どもについて、モローはフロマンタンに、自分はたいへんはっきりした観念を結びつけているが、見る者は好きなようにとって良い、と述べている(439)。幾つもの天体は、モローの晩年の他の作品にも現われるもので、『諸天球を瞑視する大いなるパン』(図220→こちら)における雲に開いた目と同じような、終末論的黙示録的な表象と考えることができる。このヘレネーの昇天という主題については、マテューがこれを、ゲーテの『ファウスト』第二部第三幕に由来するのではないか、と述べている(440)。この指摘は必ずしも納得できるものではないが、モローがもとはゲーテに刺激されたのであるにしても、その構想はモロー自身のものとなっている。 この水彩は細部までたいへん入念に仕上げされている。ヘレネーの裸身の肉付けは、細い白の線をからだ全体に、上から下まで覆ってなされており、大原美術館の『雅歌』(図320→こちら)などにも見られるが、それがここでは身体が褐色で描かれた上になされているので、ヘレネーの裸身を木彫像のように見せている。顔は一見して目鼻立ちがここでも描き込まれていないように見える。よく見れば薄く目、鼻、口が描かれているのだが、それにしても、右側の詩人の顔に比べても、描き方は薄い。その描き方も充分ではなく、右目は殆んど四角形になっている。この水彩の、宝石細工の装飾品が示すような、全体の仕上げの入念さは、この顔の不明瞭さが意図的なものであることを物語っている。あるいはそうでなければ、モローはヘレネーの顔だけ残して、他の部分を先に仕上げたのだが、いざ目鼻を描き込む段になって、もはや手を加えることができなかったのかも知れない。これはこの作品のヴィジョンの性格に由来するものである。ここでは、モローの描いてきた女性像中、最も<宿命の女>であるヘレネーが、全人類ないし全男性の代表が見守る中で、神の位置に高められている。しかしここでも、それは上昇を示すものとしては描かれていない。ヘレネーの巨大な光輪が上への動きを止めてしまい、そのような歯止めを頂いたピラミッド構成(ここにもシャセリオーの『アポロンとダフネ』(図12→こちら)の遥かな思い出を認めることができる)、そしてアモールや光線の方向が、下への方向性を作り出している。そして何よりも、ヘレネーが全身正面性において捉えられていること、構図がほぼ左右相称であることが、彼女を画面の奥から、絵を見る者描く者の方へ真っ直現われ出づるものとして、捉えさせることになる。その際顔に描き込むことのできるのは、真っ直こちらを見る目か、それとも目の無い顔かである。伏せられた目はこの場合、神としての顕現を描くものとしては、適さないと見なされたのであろう。 |
 図264 《栄光のヘレネー》 MGM.488 439. 1856年12月8日付けの手紙。Wright, Moisy, ibid., p.88. 440. Mathieu, "La bibliothèque de Gustave Moreau", Gazette des Beaux-Arts, 1978.4, p.158. |
|||||||||||||||||||||||||||
| このことを示すのが、『栄光のヘレネー』の構図及び内容と密接な関係にある(441)、『贖い主キリスト』(図267)である。ここにも頂きにキリストを配し、その下に三柱の天使と、『諸天球を瞑視する大いなるパン』(図220→こちら)に現われたものと同じものと思われる重なる天球即ち全宇宙、左右に全く同じに見える、おそらくは太陽と月を描いて、濃紺の地の上に左右相称、正面性をもって構成されている。ここで神的なものが顕われたことを示すのは、キリストではなく、あるいは少なくともキリストの顔ではなく、目を見開いた、偶像のように描かれた - 一番下の天使の頭部の描き方は、その目を除けば、ルオーの道化師たちのそれと全く同じである - 天使たちの、こちらを見つめる視線である。キリストが目を閉じ、額を伏せているのは、この作品の標題、『贖い主キリスト』によって説明されるだろう。即ち彼は、現われ来たる神自身ではなく、神に人間をとりなす、神と人間の仲介者なのである。そしてこのことはまた、彼がすぐれて<詩人>でもあることを意味している。 これに対してヘレネーは、すぐれて<宿命の女>であり、<詩人>によって見られる対象であり、ここでは彼女が神である。彼女を目を見開くものとして描くのは、『神秘の花』(図171→こちら)や『ユピテルとセメレー』(図268→こちら)の例からも、自然なことであったろう。しかしここで、以前描いた『スカイア門のヘレネー』(図263)や『エボーシュ』(図262)における、顔の無いヘレネーの存在が介入する。目の無いことも、力の表現であり得る。正面視の絵を見る者を見据える目は、神性の表現として、あらゆるものを見ていることをあらわしていたが、一切を見るということは、具体的な目を描かないということによって表わすことができる。あるいはそれ以上に、非人間的なものとして表現することができるだろう。『ムーサたちの散歩』(図246→こちら)でも神々は正面から捉えられた、顔の無い存在として描かれていた。これは習作だからではなく、その方が絵画としてのヴィジョンをより良く表現することができたからなのである。こうした事情が、入念な仕上げを示す『栄光のヘレネー』において、顔の描写に中途半端さをひき起こさせたのであろう。 『栄光のヘレネー』には、水彩の<完成作>がある(図265)。ここではモロー美術館の作品の、厳しい偶像のような特徴は見られず、ヘレネーは優雅に身をくねらせており、目を伏せ脇に首を向けた顔に描かれている。巨大な光輪も消えている。 またモロー美術館には、同じ構図の未完の油彩がある(図266)。ここではヘレネーは正面視で捉えられているが、目鼻立ちは描き込まれている。画面に対して人物が大きくなり、光輪は小さくなって上につかえている。 |
441. 竹本忠雄、ibid., p.84. 図267 《贖い主キリスト》 MGM.303  図265 《栄光のヘレネー》 1896-97、 PLM.425  図266 《栄光のヘレネー》 MGM.217 |
|||||||||||||||||||||||||||
| →[11]へ続く | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOME>美術の話>ギュスターヴ・モロー研究序説 [10] |