| [12]<[11]<[10]<[9]<[8]<[7]<[6]<[5]<[4]<[3]<[2]<『ギュスターヴ・モロー研究序説』(1985) [1] | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4.翼 - ガニュメデス、他 『ユピテルとセメレー』の1889年の油彩習作(図273→こちら)において、鷲の翼のシルエットが、セメレーの斜線を受けて、空間を切り裂くような強い効果を担っていることは既に述べた。これと同じような効果を示しているものに、『ガニュメデス』を描いた水彩の一点がある(図291)。ここでは森か雲かもはっきりしない空間の中を、白い塊まりでしかないガニュメデスを肩にのせた黒い鷲が大きく翼を拡げている。背景は濃褐色、白、黄、青、赤を大きくにじませて画面を埋めており、細かい対象は何も見出されない。右下に白い細い線からなる、枯れ木のようなものが見えるが、描かれたものなのか、絵具の亀裂によって生じたものなのかはっきりしない。おそらく褐色を主にした部分は森、下方の白は湖か川であろうが、森は右上で空と繋がってしまっている。しかしヨーロッパの冬の森の雰囲気(少なくとも日本人が考えるような)はよく映し出されている。このような風景の中に、それより僅かに濃い色で鷲の姿が描かれており、茫漠とした、しかし画面を全て埋めた空間の中に、鷲の翼の尖った形が、何事かを告げるような印象を与える。 |
 図291 《ガニュメデス》 MGM.521 |
|||||||||||||||||||||||
| ガニュメデスの主題を絵画化するに際しては、マテューが指摘するように、ミケランジェロのデッサン、正確には失なわれたミケランジェロのデッサンを写したものが出発点になった(481)。これは、既に見たより仕上げられた構図の水彩(図292)の左下に、吠えている犬がいることによってわかる。この犬は、ミケランジェロの素描を写した版画(図293)や素描に現われるもので、ケネス・クラークはこれをミケランジェロがこの主題に導入したものとしている(482)。ところが同じ犬は、ウィーンにあるコレッジオの『ガニュメデス』にも現われ、セシル・グールドは、ミケランジェロの素描を版画にした者が、コレッジオから取り入れたものとしている(483)。ミケランジェロの原作に最も忠実なものとされる、ウィンザーにある模写は、鷲とガニュメデスしか描いていない。しかし犬と風景を下方に描き込んだ模写は一つではないので(484)、ミケランジェロの原作にそうしたモティーフがなかった、と言い切ることはできない。ミケランジェロの素描は、トマゾ・カヴァリエリのために制作されたもので、1532年の末に彼に贈られた(485)。一方、コレッジオの絵は1527、8年から31年(486)、ないし32年の11月までには完成していたらしい(487)。コレッジオの方が少し早いようだが、時期は非常に近い。どちらが先にガニュメデスの主題と吠える犬のモティーフを結びつけたのか、それとも双方独立に、共通の出典から得られたのか、ここで決定することはできない。なおこの犬の姿は、地上に残された人間の低級な欲望を表わしている(488)。ガニュメデスの主題が当時、魂の昇天を意味するものと、新プラトン主義的に解釈されていたことは、パノフスキーが示した如くである(489)。 さて、ここで問題になるのは、モローの発想源がミケランジェロかコレッジオか、ということである。コレッジオの原作を見る機会はモローにはなかったであろうが、版画などでその図柄を知ることはできたと思われる。この点では、あきらかにミケランジェロの図案から、モローはその犬のモティーフを、取り入れたものと思われる。コレッジオの犬は真後ろからみられ、画面には腰までで切られ、後脚や尾は描かれていない。そして犬からガニュメデスたちへ、と螺旋状に上昇する構図が強調されている。これに対してミケランジェロの図では、犬はやはりやや後方から見られているが、全身描かれており、ガニュメデスたちとは繋がりがなく、むしろ対立させられている。モローでは、犬は真横から見られ、ガニュメデスたちとは対角線上に並べられている。モローがガニュメデスの主題の、新プラトン主義的解釈を知っていたかどうかは不明だが(おそらく知っていた)、同じような考えを抱いていたことは、ガニュメデスと鷲に光輪が与えられていることによってわかる。ミケランジェロへの手紙の中でセバスティアーノ・デル・ピオンボは、ガニュメデスと黙示録の聖ヨハネを結びつけているが(490)、モローにおいても、素描ではガニュメデスの主題と福音記者ヨハネの主題が、区別のつかないものがある(491)。 ミケランジェロに倣った1886年の水彩に続いて、モローはもう一点、同じ主題による水彩を仕上げている(PLM.343)。そこでは画面を大きくガニュメデスと鷲が占め、地面は描かれず、背景は空になっており、プラドにあるルーベンスの構図を思わせる。また、キマイラと乙女の飛翔も重ね合わされている。このようにして地面が消えていく過程で、あるいは後のヴァリエイションとして、先に見た水彩(図291)が制作された。ここでは86年の水彩に見られる、昇天を描こうとする意志は消えている。画面が横長になり、鷲は画面中央より下に小さく描かれ、その両翼がほぼ一直線になることによって、鷲は下から上へ昇るのではなく、登りようのない上から見下ろされて、滑空し、空間の中に羽搏きを響かせるのである。 |
481. Mathieu, ibid., 1984, p.104. 図292 《ガニュメデス》 1886、PLM.342  図293 ミケランジェロに基づいて、ニコラ・ベアトリゼ《ガニュメデス》 482. K.Clark, Rembrandt and Italian Renaissance, New York, 1966, p.13. 483. C.Gould, The Paintings of Correggio, London, 1976, p.274. 484. B.D.Kirschenbaum, "Reflections on Michelangelo's drawings for Calvaliere", Gazette des Beaux-Arts, no.997, 1951, p.110 註6. 485. Kirschenbaum, ibid., p.100. 486. E.Verheyen, "Correggio's Amori di Giove", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol.29, 1966, p.160. 487. Gould, ibid., pp.130-131. 488. Verheyen, ibid., p.187. 489. E.Panofsky, Studies in Iconology, New York, 1962(2), pp.212-216. 490. id., pp.212-213. 491. MGMd.680. |
|||||||||||||||||||||||
| モローの描く荒涼とした風景の中に、しばしば鳥が飛んでいる姿が描かれ、何事かを告げるかのような印象を与え、画面で起こっているできごとの神話的な性格を強調していることは先に述べた。描かれた風景の中に鳥を飛ばせている例は、決して少なくはないものと覚しく、今まで見てきた作品でも、ペルジーノの『アポロンとマルシュアス』(図5→こちら)がそうであったが、モローに特に影響を与えたのは、おそらくクロード・ロランであろう。彼の描く光に満ちた空間高く、幾羽かの鳥が飛んでいるのが微かに認められることは、稀ではない(クロードが淡彩で描いた『真実の書』の複製では、鳥の姿はよりはっきり描かれているが、1837年にはイギリスにあったこの画集を(492)、モローが見る機会はなかったと思われる)。クロードの鳥は、単に空の広さ、高さだけではなく、鳥がその中を舞う空間そのもの、そこに充ちた光などの感覚を、絵を見る者に感じさせる役割りを果たしていると思われる。クロード以外にモローにより近いところでは、シャセリオーの、会計検査院の『交易』(S.113J)、『マゼッパ』(図103→こちら)などの空にも鳥が飛んでいる。ここでは鳥は、異国情緒と結びついている。 これらの先例から取り入れられたモローの鳥は、その周囲に己れが動く空間の拡がりを生じさせ、天と地を結ぶ者として、自然の中に何事かのしるしを刻み込むのだが、晩年に鳥の王、ユピテルの鷲の姿で、画面で決定的な役割りを果たすことになる。この間、モローの鳥には遠くで小さく描かれているものが多いが、『パーシパエー』(図301→こちら)やデリラのそばにいる紅鶴(図161→こちら)、『サッフォーの死』(図44b-45b→こちらや、そちら)や『ポリュフェーモス』(図151→こちら)の巨大な鴎、聖霊の鳩(PLM.148=松方コレクションの《ピエタ》→こちら, PLM.391)、それにレダの白鳥(図180-188→こちら)など、大きく扱われ、おそらく特定の意味を与えられていると思われる。またこれらは白か、非常に鮮やかな赤や青で描かれることが多い。その意味では鷲は例外だが、神々の王の鳥、あるいは彼自身である鷲は、画面に占める面積が大きい。『プロメテウス』(PLM.111=MGM.196)の足もとには二羽の禿鷹がいるが、飛んではおらず、一羽は死んでいる。モローはここでは特に、伝承にある鷲ではなく禿鷹を選んだのであって、その理由は、「感情の論理に従って、鷲、動物の内最も気高く、最も王者の如きものを、この苦しみに耐える人物の拷問執行者にはしないであろう」(493)からである。プロメテウスを苦しめているのは、「野蛮と賎しい物質」(494)であり、禿鷹はそうしたものにふさわしいと見なされたのだろう。またモローの画面には、鴉も現われないようだ。文字通りの鳥以外にも、ヘシオドスに霊感を与えるムーサ、スフィンクス、天使たち、キマイラたちなど、翼を持った混成の存在も少なくない。 |
492. D.Cecchi, Tout l'œuvre peint de Claude Lorrain, Paris, 1977, p.84. 493. Mathieu, ibid., 1976, p.109. 494. id. |
|||||||||||||||||||||||
| 『東方三博士を追う天使たち』(図294)では、褐色の濃淡で描かれた何も無い夜の荒野を、大きな輝く星に従う東方三博士とその一行を、画面の下三分の一に切り詰め、残った広大な空間の中央に、線描で、無数の飛行する天使とその翼、光輪が描かれている。何も無い空間に、文字通り無数の羽搏きが響き渡るような印象を与える。モロー美術館の『ガニュメデス』水彩(図291)と同様に、空間とその中での翼の動きが、画面の性格を決定している。 『夕の声』(図328)では画面は縦長になるが、やはり茫洋と水平の筆致を主に、それに木や草などの垂直を加えて描かれた水辺の空間に、切り込むV字が画面を構成しており、V字の拡がった先になるのが、ムーサだか天使たちだかの鋭い、青い翼である。その幾つもの翼の響きによって、彼女たちは夕の時を自然に伝える。鮮やかな青、赤、黄、エメラルドグリーンなどとともに、絵を見る者の方に真っ直視線を向けて、水辺の空間の内に立ち現われる女神たちを描いたこの作品の内容は、『ユピテルとセメレー』(図268→こちら)のそれと全く同じであり、ただこちらの方が、より自然である。画面の四方は拡大されており、画面の両端や底の部分は、濃褐色か緑をざっと掃いているだけで、白い部分も残っている。 |
 図294 《東方三博士を追う天使たち》 MGM.797  図328 《夕の声》 MGM.585 |
|||||||||||||||||||||||
| 5.テティス - エウロペ、パーシパエー、アポロンとムーサたち、他 モローの『ユピテルとセメレー』に対して、アングルの『ユピテルとテティス』(図269→こちら)が与えた影響は、正面視、左右相称の構図、ケネス・クラークが「一個の古典趣味的家具」(495)と呼んだユピテルの姿に留まるものではない。モローの絵の鷲は、アングルの絵の鷲と、首の角度が全く同じである。フラクスマンのホメーロス挿絵(図270など→こちら)でユピテルの玉座の傍にいる鷲は、皆玉座の外の方を向いている。また、モローの絵でユピテルの肩から忽然と首を出している詩の精のモティーフは、アングルの絵の左端で、やはり唐突に首を斜めに出している、ユーノーの姿から想を得たものであろう。この二つの借用は、以前、ラ・フォンテーヌの寓話挿絵の一つとして描かれた、『ユーノーに不平を言う孔雀』(図295)の中にも認めることができる。ここでも雲の上に玉座があり、そこにユーノーが坐っている。ここでもユーノーの足もとにいる孔雀は、アングルの鷲と全く同じ角度で、首を出している。他方ユピテルの鷲はここでは、アングルのユーノーがいたのとほぼ同じ位置に配され、やはり雲から斜めに首を出している。ユーノーの持っている長い笏も、アングルのユピテルの持っている笏と比定することができよう。 しかしアングルの作品の中で最も重要なテティスの姿は、モローに何の印象も残さなかったのだろうか? ある意味では、『ユーノーに不平を言う孔雀』における、色の濃さを抑えての、アングルのスフィンクスのように視線を逸らしている、ユーノーの身体が描くアラベスクを、アングルのテティスに触発されたものと見なすことができるかも知れない。しかし、より直接的にアングルのテティスの姿を反映していると思われるモティーフを、他の作品に見出すことができる。 |
495. クラーク『ザ・ヌード』、ibid, p.197.  図295 《ユーノーに不平を言う孔雀》 1881、MGM.566b - PLM.226 |
|||||||||||||||||||||||
| モローの最晩年、1897年の年記がある水彩画、『エウロペ』(図296)においてヒロインは、やはり正面視で捉えられたユピテルの左の足もとにすがりつくようにして、右腕を上に上げており、ここにアングルのテティスの反映を認めることができよう。彼女の仰向けられた頭部の角度も、アングルのテティスとほぼ同じである。 この作品はすぐに認められるように、二年ほど前に描かれた『セメレー』のヴァリエイションとでも言うべきものである。画面は正面性、ほぼ左右相称のユピテルを中央に配し、彼はかっと目を見開いている。視線が微かに右に逸れているところも同じである。ユピテルは豪華な胸飾りをつけ、光輪を戴いている。その頂きには、翼のある花のようなものがついている。背景は星の浮く青い夜空で、ユピテルのからだから、89年の『セメレー』の油彩習作(図273→こちら)や、完成作が仕上がる以前を映した写真(図278-279→こちらや、そちら)に見られたような、雷光が走っている。画面の両端は、この度ははっきり樹木になり、そこここに大きな花や葉をつけている。花は画面の底部にも咲いている。エウロペの右側にいるのが、山羊の足の地の愛の精で、位置は異なるが、ポーズはそのままである。このモティーフが同じ97年の『栄光のヘレネー』(図264→こちら。87年の誤り)にまで遡ることのできることは、既に述べた。なお『セメレー』の地の愛の精の姿勢については、フラクスマンのダンテ挿絵の一つに由来することが、キャプランによって指摘されている(496)。 さらにこのユピテルは、四枚の翼、さらにエウロペの背中にもう一枚、どういう位置についているのかわからないが、全六枚の「セラピムの翼」(497)を持っている。そしてこのユピテルは、牛のからだに人間の頭部で、1869年のサロンに出品された『エウロペ』(図297)について、ゴーティエが指摘したアッシリアの有翼の人頭牛像の影響が(498)、顎鬚が長くなった分、69年の作品以上に顕著になっている。翼を与えたのも、同じアッシリアの遺品の示唆によるものであろう。このようにしてこの作品の主題は、『ユピテルとセメレー』と同じ聖なるものの顕現、ホルテンのことばをかりれば、「<栄光の>ユピテル= 牛」(499)なのである。ただこの作品は、仕上げは丁寧で装飾も細かいが、絵の大きさが小さい分、形態は単純化されて膨らみを持ち、ユピテルもエウロペも、『セメレー』の主人公たちほど硬直していない。 牡牛に化けたユピテルによるエウロペの誘拐の物語をモローが取り上げたのは、先に触れた69年のサロン出品作が最初だが、この作品はモローの全作品中でも、67年の『キマイラ』(図36→こちら)以上の、最もグロテスクな作品であると言うことができる。画面は丁寧に仕上げられており、それがグロテスクさをいっそう強調している。エウロペは『イアソーン』(図152→こちら)のメディアに見られた女性のタイプを推し進めたものだが、その顔の表情は媚びに近く、腰や脚は非常に重苦しい。しかしそれ以上に迫力があるのはユピテル=牛で、表面の滑らかな仕上げが生み出す印象は、殆んど堪え難いものである。アカデミックな作品が高級な芸術作品以上に、表出力が強いということの一例がここにある。ここでも胴は牛だが頭部は人間で、『ガラテア』(図144→こちら)のポリュフェーモスがいずれ示すことになる、詩人的な重々しい表情をしている。顎鬚や髪型は先に触れたように、アッシリアの有翼人頭牛像から借りたもので、牛の胴に人間の頭を与えるというアイデア自体、そこから得られたものであろう。ユピテルの頭部は光を発しており、この時既にモローは、この主題、あるいはユピテルという神の性格に、特別の意味を感じていたことを示している。『オルフェウス』の水彩(図132→こちら)を別にすれば、異教の人物に光輪が与えられたのは、これが最初であろう。頭部は胴に比して小さすぎるが、最も印象的なのは、ポール・ド・サン・ヴィクトールにショックを与えた(500)、喉垂れ肉であろう。また 67年の『キマイラ』でも後の類似のモティーフの作品でもそうだが、モローは牛の前脚は両方宙に浮かせて、後脚を両方地面につけて描き、このため常にわざとらしく静止した印象を与えることになる。画面の下部には肉の厚そうな植物が描かれており、『セメレー』の植物まで繋っていく。 |
 図296 《エウロペ》 1897、PLM.426 496. Kaplan, ibid., 1970, p.396. 497. Holten, ibid., 1965, p.125.  図297 《ユピテルとエウロペ》 1868、 MGM.191-PLM.105 498. Laran, Deshairs, ibid., pp.47-48. 499. Holten, ibid., 1965, p.125. 500. Laran, Deshairs, ibid., p.48. |
|||||||||||||||||||||||
| モローはこの作品以後、何度もエウロペの主題を取り上げるが、既に見た油彩の小品(図179→こちら)と同じように、いつも自然の牛を描き、頭部を人間のものにするのは、97年の作品(図296)まで見られない。図298 はそうしたものの一つで、構図はサロン出品作(図297)と同じだが、にじんだ水彩の明るい色彩が美しく、エウロペもより可憐な面立ちをしている。 97年の水彩で再び頭部が人間のものになったのは、晩年のモローの神秘主義的傾向とともに、ホルテンが指摘するように、『セメレー』の正面性によって、人間の頭部と牛の胸を接合することの、困難が減少したからであろう(501)。そして『セメレー』と97年の『エウロペ』が<交差>していることを示すものとしてホルテンが挙げているのが、一点の小さい油彩である(図299)(502)。ここでは細部を全く省いた厚塗りで、中央に大きく光輪をつけた上半身の人物、その右下にセメレーと同じ姿勢で、ぐったりした裸婦が描かれている。ところが、胸が丸みを帯びていることを別にしても、セメレーの左に、97年の『エウロペ』にあると同じ、白い立てられた右膝と、続く臑が見える。それ故この作品を、『セメレー』完成後の、『エウロペ』のための習作と考えることができるように思われる。しかしことは単純ではない。構図決定以前の『セメレー』の油彩習作(図275→こちら)に目を戻すと、そこでのユピテルの顔立ち、特に顎鬚が既に、アッシリアの人頭牛を範としており、ホルテンが指摘するように(503)、69年の『エウロペ』から出発していることがわかる。またこの油彩でも、89年の油彩(図→こちら)でも、ユピテルの左膝は重視されている。図299 の右膝は97年のそれに近く、また女をセメレーの姿勢で描いた素描もあるので(MGMd.100-101)、この作品の主題はエウロペであると考えてよいであろうが、女の左右が『セメレー』とも97年の作品とも逆であることが暗示するように、『セメレー』以後のものと決定し切ることはできず、『セメレー』の構想以前に、あるいはそれと平行して、『エウロペ』を正面性の構図で描く構想が進行していたのかも知れない。『セメレー』が先に完成したのは、人間と牛の混成よりも、全身人間の方がより理想的、よりモニュマンタルであると判断されたからである、と考えることもできる。 |
 図298 《エウロペの掠奪》 1869頃、PLM.109 501. Holten, ibid., 1965, p.126.  図299 《セメレー》 MGM.182 502.id. 503.id., pp.124-125 |
|||||||||||||||||||||||
| さらに牛=『エウロペ』=『セメレー』の関連に追加されなければならないものとして、『パーシパエー』を描いた油彩の一点がある(図300)。ここでも女は<テティス>の姿勢で、牛の首に上げた腕を巻きつけている。全身の体勢、足の組み方、さらに顔立ちや長い髪は97年の『エウロペ』と全く同じである。右側には地の愛の精もいる。牛も体勢、両脚の配置は同じで、ただ頭部は牛の首で、女の顔の方に頭を寄せている。牛の背後には垂直軸をなす木が画面の上まで届いている。 パーシパエーの主題も、モローは1860年の水彩(PLM.47)以来繰り返し取り上げており、先に見たデュルー・コレクションの水彩(図301)もその一つである。これらは風景の比重、画面が縦長か横長か、パーシパエーが全裸か何か衣を着ているか、片腕を上げているか下げているか、ダイダロスの位置とポーズなどの点で多少の違いはあるものの、全て前景にパーシパエーとダイダロス、二人の背後に青銅の牛を配し、奥の風景から白い牛が現われる、という設定で一致している(他に PLM.48=PLM'98.119)。この点で図300 は別の系列に属し、さらにパーシパエーが青銅の牛の中に入るのではなく、牛と直接抱き合っているという点で、伝承とも喰い違う。おそらくここには、彼女の無邪気な顔立ちや長い髪が暗示するように、モローの彼女に対する深い同情がそこにある。牛の首の傾きにもそのことを読みとることができる。地の愛の精の存在が示すように、この作品は晩年のものだと思われるが、晩年のモローのユピテルに対する関心が、ユピテルの化身としてエウロペの図像の中で描いてきた牛と、パーシパエーの牛とを重ね合わさせたのであろうし、この牛が物語の中で、元来神の送ったものであったことを思い出したのかも知れない。デュルー・コレクションの水彩のように、以前の図像で彼女を美しい風景の中に配した、ということが一つの引き金になったのかも知れない。デュルー・コレクションの作品は、モローにとっても会心の作であっただろう。彼はパーシパエーについて書いている(504)、 |
 図300 《パーシパエー》 MGM.75  図301 《パーシパエーと牡牛》 1876-80頃、MGM.inv.15504 504. MGM.75. |
|||||||||||||||||||||||
| 「蒼褪めて偉大な人物たち、恐るべき、暗く荒廃した、宿命の愛人たち、 あきらかにここには、女性や獣性に対する単なる軽侮ではない、仰々しいまでの深い同情がこもっており、以前の図像よりも、牛と女が抱き合う構図を頭において書かれたものであろう。これまで見てきた一連の構図の中では、このパーシパエーの図が最も早く描かれたものと思われ、ここから牛とユピテルの結びつきを通して、エウロペ、そしてセメレー、あるいは両者が絡み合って展開していったものと考えられる。 |
||||||||||||||||||||||||
| さて、パーシパエーの主題の見直しを促したものとして、やはり以前のキマイラの図の解釈に変化が生じたことが、その原因の一つであると推察される。この変化については既に述べたが、ここでそれが関係してくるのは、67年のキマイラの構図においても、パーシパエー同様娘が怪物の首に腕を巻きつけているからである。ここではまだ、アングルの『テティス』の影響を読みとることはできない。同じモティーフは後年の『バラッド』(図198→こちら)にも現われ、そこにドラクロワの『ルッジェロとアンジェリカ』(図197→こちら)の影響を見ることができることは既に見たが、67年の『キマイラ』では、ドラクロワとは別のより直接的な典拠を挙げることができる。図37はルーヴルに展示されているローマの石棺で、両端に牛の首に片腕を巻きつけている娘の姿が彫られている。彼女は飛びつくようにからだを浮かし、片脚の膝を曲げて、足を天に上げている点まで『キマイラ』の娘と同じである。彼女らの下には海の波が彫られている。このルーヴルの石棺についてはきちんと調べていないのだが、実はこのモティーフは他にも見られる。ヴァティカンにあるやはりローマの『ネレイデスの石棺』(図38)がそれで、中間の図柄は異なるが、端には全く同じモティーフを認めることができる。ケネス・クラークはこうしたパターンは、古代世界全体にひろまっており、同じ図様から作られたものであろうと述べている(505)。モローがそうしたものを見て、『キマイラ』の構図に利用したことは、確実と思われる。またこのことが、67年の『キマイラ』の主要モティーフが、『パーシパエー』以下の牛と女の組み合わせに結びついていくことも説明してくれる。そして後の構図では、67年の『キマイラ』の不安定さが避けられ、正面性の構図へと向かう過程の中で、ローマの石棺の影響がアングルの『テティス』の影響に移っていったのだと思われる。 |  図36 《キマイラ》 1867、PLM.89  図37 ローマ時代の石棺  図38 ローマ彫刻;ネレイデスの石棺 505. クラーク『ザ・ヌード』、ibid., pp.353-354. |
|||||||||||||||||||||||
| 『テティス』の影響も、必ずしも新しいものでないことは、『アポロンのもとを立つムーサたち』の水彩(図303)が教えてくれる。この主題の正確な題は、『ムーサたちは父アポロンのもとを立ち、世界を照らしに行く』というもので、この主題についてモローは書いている(506)、 「夜だ。美しい旅する鳥たちはその巣を離れる。 神は、霊感を受けた姿勢で動かず、己れの内に引きこもり、自分を取り囲むものを越えた思考を見下ろしているかのようである。彼の娘たちは彼から、霊感と信仰の息吹を受け取る、そして彼女たちは遠方に赴く、己が内に様々な形の神的な理想を抱き、遠く世界の上に、詩人たちを産み出すこれら生命の種子を蒔くのだ」。 この主題のための油彩(図302)には1868年と記されているが、未完に終わっている。事実左の一番前にいるムーサの衣の赤は、後期以降のものであることを感じさせ、全体に衣服や玉座には<入墨>が施されている。画面は四方拡張され、特に上部が広くなっている。 この主題のための水彩の一点は(図303)、画面が拡散される以前の構図を示し、人物の配置、ポーズもほぼ一致する。主な違いは、左手前のムーサの腕の位置と首、視線の角度、アポロンが白目になっていること、そしてアポロンに一番近いムーサが、左腕を伸ばして彼の顎に触れていることである。このムーサのポーズはあきらかにアングルのテティスを思わせ、その点では今まで見てきた『パーシパエー』(図300)や97年の『エウロペ』(図296)以上である。パーシパエーもエウロペも、からだの画面側の腕を上げていたが、このムーサはテティス同様、奥の左腕を上げている。パーシパエーとエウロペは頭部が四分の三観で捉えられていたが、ここではプロフィール、という以上に目や口が見えないほど向こう側にひねられている。アポロンは黒目が見えないが、完全な正面性で捉えられている点では、視線が僅かに右に逸れている『セメレー』や『エウロペ』以上である。 油彩ではこのムーサは腕を上げていないが、しかし腕ははっきり描かれておらず、未決定のままなのか、それとも後から塗り直したのか、アポロンの身体は全て仕上げられており、腕を上げるポーズは採用されていないらしい。水彩は、線はぎこちないもののよく形態を単純化し、賦彩も丁寧に施されている。色彩は鮮やかで濃厚なものは用いられず、線の機能を邪魔しないよう配慮されている。この水彩が油彩に着手する以前に制作されたものと決定することはできないが、いずれにせよ画面が拡張される以前で、おそらく油彩に取りかかる直前のものではないかと思われるとすれば、異教の人物に光輪を与えることは、『オルフェウス』水彩(図132)の64年という年記を信用しないとすれば、『エウロペ』サロン出品作(図297)より早いか、少なくとも同時期にここでなされていたことになる。 |
 図302 《ムーサたちがアポロンのもとを立って、世界を照らしに行く》 1868、MGM.23  図303 《アポロンとムーサたち》 MGM.334 506. MGM.23. |
|||||||||||||||||||||||
| 『アポロンのもとを立つムーサたち』の構図はアポロンの正面性と光輪、『テティス』との関係、この世界へ神的なものがやって来るという主題、そしてその神的なものが詩と結びつけられている点などで、『セメレー』に繋がっていくものだが、これは同じ構想のための別の水彩(図304)では一層明瞭である。筆致が粗いためか、色彩がより鮮やかなこの水彩は、先の二点とは異なる構図を示し、最終的な構図が決定する以前の段階を示すものと思われる。ここではアポロンは、アーチ状の岩の上にある玉座に坐り、ムーサたちはその下に散らばっている。このアーチ状の岩とその上の人物というモティーフは、あきらかにルーヴルにあるマンテーニャの『マルスとウェヌス(パルナッソス)』(図305)から借りられたものである。モローはこの作品を模写しており、右端のヘルメースとペガサスの組み合わせが、『一角獣と女』を描いた油彩の一点に用いられていることが、ホルテンによって指摘されている(507)。他に、ヴァティカンのラファエルロの『パルナッソス』(図41→こちら)の思い出もあるかも知れない。 アポロンはここでは、最終構図では下半身を右に向けているが、全身正面向きで玉座に坐っている。彼は強い光輪を放ち、玉座の両側には柱が立ち、そこから植物が生えている。画面の両端にも木が立っている。玉座を支えるアーチ状の岩を、『セメレー』の「底も頂きもない、宙空に浮く巨大な建築」と比較することもできる。 このように中期の、『アポロンのもとを立つムーサたち』や『エウロペ』などの、神性に関する絵画が、晩年の『セメレー』等の作品に繋がっていく。 |
 図304 《アポロンとムーサたち》 MGM.292  図305 マンテーニャ《パルナッソス》 1497 507. Holten, ibid., 1965, p.127. |
|||||||||||||||||||||||
| 6.ヘカテー i. 異形の目、目の増殖 既に触れたように、『ユピテルとセメレー』の中でユピテルの見開かれた目は、真正面から絵を見つめているのではなく、微かに右に逸れている。これはセメレーの配置によって左右相称が破られたことに対して、均衡をとるためであろう。またユピテルとセメレーの描写の硬直ぶりも、目を逃れないわけにはいかない。これも超人間的な性格を強調するためである、と解することもできる。しかしこの画面の中でより表現力が強く、絵を見る者をじっと見据えている者がおり、それは画面左下のヘカテーである(図306)。 |
 図306 図268の部分 |
|||||||||||||||||||||||
| 大きく見開かれた緑の目は、絵を見る者を呪縛しようとしているようにも、目の前にあるものを何も見ていないようにも見える。このような目と視線の表現については、今まで何度も述べてきた。こうした視線は、その視線を送り出す主体が、その視線によって見られる、絵を見る者の属している世界とは、全く対極にある世界のものであることを意味している。そして絵を見る者とは人間なのだから、彼を見据える者とは人間でないもの、この世界とは別の世界のものである。また絵とはそれ自身で完結した宇宙であるから、その宇宙の内にある何か特定の対象ではなく、その宇宙とは別の宇宙を真っ直見据える視線とは、絵の目に立つ者一人一人を見つめるとともに、絵の前に立つ者を誰でも全て見つめるものでもあり、見られる宇宙全てを見ているのである。これは聖なるもの、神の視線である。またこの視線は、絵を見る者によって見られるのではなく、絵を見る者を見据える、というそのことによって存在している。即ちそれは、画面から絵を見る者へ、という一方向性を本質としており、言い換えれば、現われる、ということにおいて存在しており、これが画面の平面性を保護してもいる。この視線の主は、絵を見る者の対極にいる、その感情を移入することのできない、絶対的な客体であるとともに、見られるということによって存在するのではなく、見るというただそのこと、存在するというそのことそのものによって存在する、絶対的な主体でもある。他の何ものによっても規定することも分析することもできないものとは、神に他ならない。神とは、ただ神であるということによって神なのであり、それが善であるか悪であるとかは、それ以後の二義的な価値付与にすぎない。 このような視線による神的なものの表現は、いうまでもなくモロー一人のものではなく、ヨーロッパにおいては中世の美術が展開させたものであるが、これまで見てきた様々な視線のタイプが既に、この世とは別の世界を見るものとして表現されていた。これはある意味で、自分とは別の何かを見るという、視線の本質によるものなのかも知れないが、このような別の世界に向けられていた視線の表現が、その視線の方向を画面を見る者の方へ向けることによって、もとの視線によって見られていた、別の世界のものそのものを表現することに、たやすく移行したというのは、理解できることである。この背後には、モロー個人の、そして19世紀という動揺する時代の、この世界を超越するものを求めようとする傾向があることは言うまでもない。 神的なものをその属性以前の、ただそれ自体において現われるものとして捉えるということは、そのような把握をする者が、常時神性の現前を直接的に知っているということ、あるいは、日常的な生活とは全く対立したものとして、神的なものを求めているということ、のどちらかを前提にしている。モローと19世紀の人間たちは後者であって、日常的なもの物質的なもの現世的なものと、超越的なもの精神的なもの彼岸的なものとが、二元的に分裂してしまった時代の、日常生活と対立して、神秘主義をそれ自体として、観念的に求める傾向によっている。これは同時に、そうした精神が深く物質性に縛りつけられていることをも、その裏面として意味している。このことがモローにおける、上昇のヴィジョンの劣勢の理由ともなる。彼は自分から昇っていくことができないので、向こうがこちらへやって来るのを待つしかないのである。この世界と向こうの世界は、常に主体と客体として分離されており、その間を自由に往き来することはできない。天界へ上昇することはできないので、彼は地下、冥府へ下降することによって別の世界を見出そうとする。上でも下でも、「この世の外ならどこでも」同じことである。ここから彼の地中世界、宝石世界、「結晶世界」(J.G.バラード)のヴィジョンが生じる。それが一方では抽象エボーシュのマグマの流れを描かせ、他方では『セメレー』以下の宝石細工を彫琢させる。 |
||||||||||||||||||||||||
| ヘカテーのやや前屈みの、正面から捉えられた姿勢、二つの翼の配置は、フラクスマンの『イーリアス』挿絵の内、ユピテルの罰を逃れようとする眠りを描いた場面の(図307)、中央を大きく占める夜の姿から得られたものであろう。また既に触れたように、『セメレー』の地の愛の精の体勢は、キャプランによってフラクスマンのダンテ挿絵の一点に由来することが指摘されているが、それとともに、この場面の逃れようとする眠りの姿の影響をも、あわせ考えることができる。 フラクスマンの夜は、視線を眠りのいる右方にやり、またその瞼は重た気に描かれている点で、モローのヘカテーとは異なる。この点でモローのヘカテーの目の表現に影響を与えたと思われるのが、先に『眠り』(図136→こちら)のポーズへの影響をピカールが指摘していることを述べた、システィナ礼拝堂天井画のミケランジェロによる一人物である(図138→こちら)。フラクスマンの夜には見られないヘカテーの右腕の配置も、ミケランジェロの図の右腕の配置とほぼ一致する。なおモローのヘカテー像は、視線の方向が異なるにもかかわらず、ブレイクのやはり『ヘカテー』(図308)と似通ったものを感じさせる。これは双方が同じミケランジェロの人物像から出発しているであろうことによるものと思われる。むしろ両者が同じ原典から別々に出発して、同じヘカテーというイマージュに達した点が興味深い(補註507)。 |
 図307 フラクスマン《『イーリアス』の挿絵》より  図308 ブレイク《ヘカテー》 補註507 現在ではブレイクの水彩の主題はヘカテーではなく、《エニサーモンの喜びの夜》とされています。『ウィリアム・ブレイク展』図録、国立西洋美術館、1990、pp.137-138 / cat.no.31 |
|||||||||||||||||||||||
| 『ユピテルとセメレー』の画面の中で、絵を見る者に視線を注いでいるのは、ヘカテーだけではない。彼女とともに、彼女の周りにいる諸々の化生たちが、闇の中からこちらを見つめている。深淵に位置する闇の世界だけではない。両端の柱を伝って、無数の小さな存在が光輪をつけて、暗がりの中から湧き出している(図309)。これらは光輪のように、曲線で閉ざされた小さな形態に、強い輪郭で閉ざされることによって、いっそう厚くなるかのように、絵具を厚く盛り上げられている点で共通する、植物の葉や花と一緒になって、画面の最上部まで昇っている。高いところに出て一気に炸裂するかのように、画面の頂き、玉座を支える柱の上で咲き開いている。セメレーの翻る髪の下からも、なかば隠された顔が真っ直こちらを見つめている(パルミジャニーノの『首の長い聖母子』で、一人こちらを真っ直見つめている、顔だけ描かれた娘の奇妙な効果を思い出させる)。詩の精がユピテルの肩から唐突に顔を出すのも、画面全体にうごめく小さな形態の増殖運動の結果であり、それら全ての運動が、ユピテルの頭部に集約され、後光と見開いた目の視線として爆発し、画面を完成する。 |  図309 図268 の部分 |
|||||||||||||||||||||||
| 『ユピテルとセメレー』という作品において、細部に付された寓意的意味以上に、小さな細部が無数に集積されているという、造形上の構成の方が重要なことは先に述べた。またモローの作品、特に晩年のものにおいて、光輪が単なる指示の記号ではない、その円という完結した形態という、造形的な性格においても重要であり、特にそれが数多く描かれる時、画面内の小さな閉ざされた形態が、増殖していくような連動するリズムを作り出すこと、それが<自然の証人たち>のモティーフと相重なって、空間の非日常的な活性化を暗示すること、そして円という形態が目のイマージュと一つであることなども、既に述べた。『ユピテルとセメレー』はこのような要素が一つに集中され、凝縮されてでき上がった作品なのである。この絵の真の主人公は、ユピテルやセメレーではなく、その小ささと形態が閉ざされていること、厚塗りのマティエールとその輝き、正面視と平面性などによって、無限に増殖していく<証人たち>なのである。この意味では、モローがその註釈の中で描いてみせた、汎神論的な自然の活性化のヴィジョンも、絵画的に表現され得ていると言うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| ところでモローは、先に引いたものより前に、絵を購入したゴールドシュミットのために書いた註釈の中で、次のように語っている(508)、 | 508. Kaplan, ibid., 1970, p.412 註47. |
|||||||||||||||||||||||
| 「しかし、一切が息づき、一切が新しい命を取るように見える一方で、玉座の足もとの |
||||||||||||||||||||||||
|
しかし、とモローの単語を繰り返そう、このような上なる領域と下なる領域の二分を、絵の中に認めることはできない。両端のスフィンクスの視線に守られた、ヘカテーのこちらを見る目に始まって、彼女の周囲の化生たちの閉ざされた形態、光輪から、無数の小さな形態を伝わって、遂にユピテルのこちらを見る目に至る、一貫した連動が、画面全体を統一している。シッフはこの絵に、浄い精神と不浄の物質との、グノーシス・マニ教的二元論が表わされていると見るが(509)、これは少なくとも註釈ではなく、絵に関する限り、誤りである。二元論は確かに存在する。しかしそれは、絵の内部にあるのではなく、上と下、精神と物質の間にあるのでもない。同じ平面上に立って対峙する、絵と絵を見る者、別の世界とこの世界、神々と人間、両者のそれぞれの視線の間にこそ、対立が存在するのである。そしてこの対立はある意味で、19世紀絵画が進行させて来た、絵画の平面性の一つの帰結でもある。 |
509. Schiff, ibid., p.383. |
|||||||||||||||||||||||
| 小さな存在たちに与えられた無数の光輪の表現は、先に述べたように、モロー自身の以前の光輪の用法を展開させたものだが、そしてここでは、中世の作例を参照したであろうが、特に闇の化生たちにおいて、光輪を幾つも並べて効果を上げるというモティーフは、中国か日本の仏画の表現に影響されているのではないかと思われる。先にある仏典の一節を引いて、小さなものから、無限に多くの存在が増殖していくさまの描写が、『セメレー』の細部の、やはり小さな存在が次々に増殖していく表現と、類似していることを述べた。あのような記述は多くの仏典に見出されるであろうが、モローがそうしたものを知っていたとは、考えにくい。しかし何らかの、浄土変相図のようなものを、何かの機会に、実物でなく図版ででも、見ることはできたであろうと思われる。モローが『アレクサンドロス』(図96→こちら)制作にあたって、インドの事物を多く画面に取り入れていることは、既に述べたが、そのような例は勿論あれだけには留まらない。そして仏画の中に、小さく描き込まれた無数の仏菩薩に付された光輪が、<必要な豊かさ>に加えて、「構図に宗教的な性格を与える」という、造形的な効果をあげていることに、気付いたであろう。また極東の神々の異国的な顔立ちは、失礼ながら小さな存在たちに、非日常的な性格を与える役に立つとも考えたであろう。これらの小さな存在たちは、古典的な意味での理想的な顔立ちをしていない。もっともそのタイプは、モンゴロイド的と言うよりもっと荒々しいもので、この作品に限らずモローの描く世界は多くそうなのだが、ロバート・E・ハワードらヒロイック・ファンタジーの作家たちが思い描いた、遥か古代の、血みどろの宗教と文明を思い起こさせる。こうしたヴィジョンの源泉は、19世紀ゴシック・ロマンスとロマン派にあるのだが(補註 ゴシック・ロマンスを19世紀のものというのは誤りで、18世紀後半以降とするべきでしょう)。 | ||||||||||||||||||||||||
| モローは細部の習作を多く残しており、それらはしばしば線のアラベスクで、装飾的な性格を示しており、完成作では暗がりの中に埋もれてしまったり、絵具の上から<入墨>として描き込まれたりしている。図310
はヘカテーのすぐ右上の部分のための習作で、多くの豊かな装飾をつけた異様な顔を積み重ねている。完成作では暗い褐色で埋められ、細部をはっきり見極めることはできない。画面のごく小さな部分のために、ここまで細かい装飾を描き込むのは無理な話で、モローは完成作では、色彩を大きく掃くことによって、線と色彩が干渉し合うことを避け、両者を並存させたのである。素描では、線の装飾的なアラベスクをそれ自身のために、賦彩のことを考えずに、探求している。素描に長々と書き込んであるのは、辞書から、「月、夜の神性、夜、異教での太陽に次ぐ、最も偉大な神性」に関する様々な知識を写したものだという(510)。図311
は画面右下のスフィンクスの、すぐ左の部分の習作で、これも完成作ではかなり暗くなっている。女の後ろにいる、三頭の怪物は、コラン・ド・プランシーの『地獄辞典』から取られた、悪魔アスモデウス(図312)であることが、キャプランによって指摘されている(511)。この図柄の素描は他にもあり、それらは『淫蕩』と題されている。図313
は完成作には用いられていないようだが、ホルテンはユピテルの右の有翼像群のための習作と述べている(512)。下半身魚の、有翼のセイレーンがいる。小さな星が幾つもある。画面左端の大きな有翼の人物も、輝く大きな赤い球体に乗っており、これが黙示録的な状況を表わすものとして、モローの他の画面にも現われることは、先に見た。 |
 図310 《『セメレー』のための習作》 MGMd.3378 510. Mathieu, ibid., 1976, p.181.  図311 《『セメレー』のための習作 - 淫蕩》 MGMd.1553  図312 コラン・ド・プランシー『地獄辞典』への挿絵 - 《悪魔アスモデウス》 1863 511. Kaplan, ibid., 1970, p.398.  図313 《『セメレー』のための習作》 MGMd.3396 512. Holten, ibid., 1965, p.152. |
|||||||||||||||||||||||
| ii. 正面像 - セバスティアヌス、天使たち、十字架 図314 は真正面から見られた青年の顔を大映しにしている。彼の目は大きく見開かれ、焦点があっていないように見える。額や左目の下に、直線が立って汗のようなものが出ているのは、矢と血である。全体に強く濃い線が強調され、形態は硬張った仮面のようで、肉付けも丸みを表わしていない。 図315 はピュヴィスの素描で、やはり正面から捉えた顔を大きく描いている。こちらは目を天に向け、顔は丸みがあるが、その形態が強い線で描かれた、幾何学的、抽象的なものである点は変わらない。肉付けはモロー以上に、施されていない。この素描は、採用されなかった、パンテオンの装飾のための習作と考えられている(513)。 モローとピュヴィスの間では、直接的な関係を考えることもできるが、こうした例は他にもある。図316 はアングルの『ゴードリー夫人』で、やはり正面から捉えた顔のアップである。彼女の重そうな瞼と、反対の方向を向いた眼球は、人間ではなく蛙の肖像を見ているような印象を与える。ワシントンのナショナル・ギャラリーにある『モワテシエ夫人』像も、全身像に近いものだが、頭部は正面から捉えられている。アングルは他にも聖人像などで同様の扱いを行なっており、『ユピテルとテティス』(図269→こちら)についても同様である。 このような正面性の強調とそこから生じる異様な印象は、ブグローの作品などにも見られ、19世紀という様式の動揺期が産み出した現象の一つであると考えられる。勿論こうした処理は中世の聖者像に遡るものであり、その後も大衆芸術の領域で生き続け、今も生きているものだが、19世紀にはそれがかなり目のつく部分に現われて来たのである。これは宗教的なものが世俗化したものというより、むしろ世俗的なものが、表出性の強調を通して、今は崩壊してしまった宗教的権威に代わる、何か未だはっきりしない、宗教的なものを求める傾向の現われであると思われる。モローやピュヴィスの場合は、直接中世の作例を参照したものであろうが、特にモローの場合、既成の体系に頼るのではなく、自分自身で新しい綜合を試みていたことは、『レダ』や『セメレー』の註釈(→こちらや、あちら)に、はっきり読み取ることができる。 |
 図314 《聖セバスティアヌス》 MGMd.3958  図315 ピュヴィス《女性の頭部》 513. Puvis de Chavannes, ibid., p.140.  図316 アングル《ゴードリー夫人》 |
|||||||||||||||||||||||
| 先のモローの素描は、聖セバスティアヌスの殉教を描いた構図(図317)のための習作で、油彩の画面でも、画面の半ば以上を、正面から捉えられたセバスティアヌスを腰まで、大きく描くために用いており、セバスティアヌスは素描と同じように、目を見開いている。右の奥に小さく、弓を引く兵士たちと、画面奥に進む、騎馬の軍人たちが見える(補図317)。この構成はドラクロワの『ヤコブと天使』(図318)から得たものと思われるが(補図318)、最前景の人物と後景の人物の、尺度の急激な飛躍による対比、というモローには珍しいモティーフを採用している。これは『アレクサンドロス』(図96→こちら)にも見られたものだが、ここでは画面の中心を構成するものにまでなって、主題の劇的、と言うより非日常的な性格を強調している。モローはセバスティアヌスの題材を繰り返し取り上げており、先に見た彼の背後から天使が何ごとか告げるという構図(図210→こちら)もその一つだが、殉教の場面も描いている。そこでも木に縛られたセバスティアヌスに、離れたところから兵士たちが矢を射かける、という設定がとられるが、セバスティアヌスはもっと小さく、横長の画面の左端に配され、より自然な構図になっている(PLM.126→こちら, MGM.76 など)。図317 はそうした構図から出発した、後のものであろう。 |
 図317 《聖セバスティアヌス》 MGM.214  補図317 図317の部分  図318 ドラクロワ《ヤコブと天使》 1861  補図317 図318の部分 |
|||||||||||||||||||||||
| モローが、絵の中の人物が絵を見る者を見つめる、というモティーフを形成するにあたっては、勿論宗教画の伝統が与って力あったであろうが、今までの視線のモティーフの場合同様、シャセリオーの影響を考えることができる。焼失した1841年の『トロイアの女たち』(S.90)や、会計検査院の『沈黙』像(図319)、『水浴を終えた女』(図165→こちら)の、傾げた首からこちらを窺う視線は、大原美術館の『雅歌』(図320)やサロメ連作の『女と黒豹』(図166→こちら)に、そのまま繰り返されている。またアルジェリア旅行以後シャセリオーの東方の題材を扱った作品には、モティーフのスケッチ的性格もあってか、こちらを真っ直見つめる強い視線が、しばしば現われるようになる。しかしこのような視線のモティーフで、モローに最も影響を与えたのは、『二人の姉妹』(図321)と『ラコルデール神父』(図322)という、二点の前期の肖像画であろう。この二点の写真を、サン・メルリ教会の装飾のそれとともに、モローは自宅に飾っていた(514)。この二点の作品では、やや堅い形態で、肉の薄そうな骨張った人物が大きく、垂直性を強調して描かれ、肉のない顔から大きな目が、絵を見る者を真っ直見つめている。シャセリオーにおける、人物の目の大きさの意味については既に述べた。前期の未だモニュマンタルな充実感を示さない人体が、衣服を着けていること、肖像画であることなどのため、裸婦でシャセリオーが見せる柔らかい量感ではなく、堅い形態で捉えられ、それが大きな目のもつ表情がはっきり視線の対象に据えられたことと相俟って、視線に非常に強い表出力を与えている。 モロー晩年の、やはり堅い線と正面性で捉えられた自画像(図323)を除けば、肖像画という性格上、この二点の作品がモローの作品に、直接反映されているのを認めることはできない。しかしモローが正面から見つめる強い視線をその作品に取り入れる時、シャセリオーの二点の肖像画の同じ表現が、心のどこかで思い出されていたと考えることは、意味の無いことではない。 |
 図319 シャセリオー《沈黙》 1848、S.113H  図320 《雅歌》 1893、PLM.399  図321 シャセリオー《二人の姉妹》 1843、S.95  図322 シャセリオー《ラコルデールの肖像》 1840、S.72 514. Mathieu, ibid., 1976, p.32. 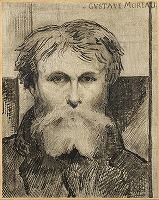 図323 《自画像》 MGM.234 |
|||||||||||||||||||||||
| 正面性のモティーフが、モローの作品の中で重要な位置を占めるようになるのは、少なくとも完成作においては、専ら晩年においてであり、その集中的表現は『セメレー』に実現している、と考えてよい。『セメレー』に至る展開の中で、重要な先例をなしていると思われるのは、1878年の万国博覧会に出品された作品中の二点である。その一点は『ヤコブと天使』(図324)で、豪華な装飾のついた衣を着た天使が、翼を拡げ、後光を輝かせ、厳かな姿勢で、ほぼ正面から捉えられている。彼は目を大きく見開いている。ただしその視線は絵を見る者の方に向けられたものではなく、むしろ放心した表情を示している。モローはここで、ヤコブの努力を対象の無いもののように描くことによって、神の力の大きさを表わそうと考えたのだが(515)、その結果は、モローの描くヤコブの奮闘同様空しいものとなっている。これは、対峙する視線の構図から正面性の視線の構図へ移行する段階で、両者がヤコブの腕のように、ぶつかることなく交差してしまったからである、と考えることができる。 この主題には水彩のヴァージョンがあるが(図325)、ここでは天使は目を閉じており、油彩の天使の硬直したポーズと異なり、優雅に身をくねらせている。この水彩は、流暢ではないが形態を単純化する、線のアラベスクを主眼にしており、そのために色彩は抑えられ、塗りは丁寧だが、水彩の軽快さを活かしたものになっている。色彩が線に従属して画面が構成されている例で、油彩の重苦しさと著しい対照をなしている。 |
 図324 《ヤコブと天使》 1878、PLM.170 515. id., p.132.  図325 《ヤコブと天使》 1878頃、MGMinv.13988 |
|||||||||||||||||||||||
| 『ヤコブと天使』と同じ時に発表された『ダヴィデ』(図326)は、やはり豪奢な衣装をつけ、後光をつけた天使を描いており、画面に対する大きさは小さいが、視線は真っ直こちらに据えられている。彼の画面での位置は、『セメレー』におけるヘカテーのそれに近いものである。しかしヘカテーでもそうだが、ここでは画面から少し奥に配されているせいもあって、天使が絵を見ている者を見つめているのか、それとも目の前にあるものを何も見ず、心の内に思いをこらしているのか、決定し切ることはできない。見開かれた目、というものにはいつもそうした曖昧さがあり、これが非日常的な性格を与えることにもなる。なおこの作品は、非常に丁寧に仕上げられたものだが、建築物の細部は、<入墨>で処理されている(補図326-1, 2)。完成作においても、色彩の力を弱めないために、モローが<入墨>を活用したという例の一つである。 |  図326 《ダヴィデ》 1878、PLM.171  補図326-1 図326の部分  補図326-2 図326の部分 |
|||||||||||||||||||||||
| 他に完成作の中では、1891年の『オレステース』(図327)が、正面性、神々の出現の主題を扱っている。この作品は、モローの晩年の完成作における、厚塗りのマティエールと形態の硬直を示す典型的な例だが、神殿に逃げ込んだオレステースの頭上に、復讐の三女神が現われた場面を描いている。ここでのオレステースと女神たちの関係は、二年後に描かれる『詩人とセイレーン』(図22→こちら)と全く同じで、オレステースのポーズも、『詩人とセイレーン』の詩人とともに、ミケランジェロの『エヴァの創造』中の、アダムの姿に由来することがピカールによって指摘されている(註83 を見よ→こちら)。 ここでエリニュエスたちが正面から、三人が一つになるように描かれていることについては、ルナンがこれをインドの |
 図327 《オレステースとエリニュエスたち》 1891、PLM.395 516. Renan, ibid., 1899, no.22, p.419.  図329 《ヨブと天使たち》 MGM.288  図330 ドラクロワ《ゲッセマネのキリスト》 1826 |
|||||||||||||||||||||||
| モロー美術館に残っている作品の内では、既に1868年の『アポロンのもとを立つムーサたち』(図302)に、正面性の構図が現われていた。ただそこでは、ムーサたちの様子は未だ優雅な、余裕のあるものであり、正面性の構図、神性の主題が集中的に取り上げられるのは、晩年になってからと思われ、そうした例はこれまでも、何点か見てきた。1890年前後、『エウリュディケの墓のオルフェウス』(図239→こちら)をはじめとして、しばしば表現主義的と評される、一連の作品が産み出されている。これが全て、『エウリュディケの墓のオルフェウス』のように、アレクサンドリーヌ・デュルーの死と関係があるとは言えないだろうが、この中にも正面性の構図によるものが幾つかある。『ソドムの天使たち』(図331)もその一点で、『オイディプスとスフィンクス』(図1→こちら)の場合と同じようなシルエットを描く風景が、濃褐色のトーンで、平面的に描かれている。細部は全く示されていないが、画面下半の中央に町が見え、数箇所で煙や火を出している。大きく開けた、何も描かれていない、白のベタ塗りの空には二体の後光をつけた天使たちが現われる。彼らも殆んど細部を描かれず、ただ左の天使が真っ直に立てる剣が、空を切り裂いて、この真っ白な空間を現出させたかのような印象を与える。この構図のために、鉛筆の素描の上に水彩を施した習作(図332)が残されており、そこでは天使の顔などが描き込まれているが、それ以上の細部は描かれていない。ただ油彩が、線を用いない、油彩の濃淡とマティエールだけで描かれていたのに対し、ここでは勢いよく走り回って、天使たちや岩山を描き出す、線の動きが主になっている。なおこの構図は、ブレイクのダンテ『地獄篇』のための、挿絵の一点(図333)を思い起こさせる。 |  図331 《ソドムの天使たち》 MGM.81  図332 《ソドムの天使たち》 MGMd.828  図333 ブレイク《『地獄篇』への挿絵》 |
|||||||||||||||||||||||
| 『パルクと死の天使』(図334)も1890年頃の作品で(517)、『ソドムの天使たち』同様、死をもたらす天使が、光輪をつけ,槍を上向きに立てている。この作品は、『エウリュディケの墓のオルフェウス』や『ソドムの天使たち』と異なり、塗りが厚く、稠密で、マティエールが冷たい輝きを発している。山や地面の部分は、パレットナイフで細かく、絵具を捏ね上げたような表面を示し、パルクは絵具を厚く塗った上から、ナイフで縦に何度も刻まれている。死の天使もやはりパレットナイフを用いられており、それが彼の姿を揺らめくように見せている。空を描く筆致も、特に右側は激しい動きを示している。このような絵具の物質性を強調したマティエールは、しかしそれぞれの色彩が割り当てられた対象をはみ出すことなく、稠密に塗り込められており、これが色調とマティエールの冷たさ、死の天使の震えるような表面の処理と相俟って、ここに描かれた神性の、戦慄すべき性格を表現する。青みがかった灰色の冷たい空の中で、光輪の黄が、内にこもったような輝きを発している。なおこの作品の構図は、ドーミエの『ドン・キホーテ』を思わせるが、モローにそれを見る機会があったかどうかは不明である。図335 はその一点だが、この作品の褐色の暖かい調子、素早い筆触を、モローの作品のマティエールの冷たい輝きと、比較すると興味深い。 |  図334 《パルクと死の天使》 MGM.84 517. Mathieu, ibid., 1976, p.161.  図335 ドーミエ《ドン・キホーテとサンチョ・パンサ》 |
|||||||||||||||||||||||
| 『ソドムの天使たち』も『パルクと死の天使』も、神々の性格の表現の多くを、顔に目鼻立ちが描き込まれていないことに負うている。このことの意味については、『栄光のヘレネー』(図264→こちら)に関して述べたが、こうした表現が最大限に発揮されているのが、やはり同じ頃に制作されたと思われる、『十字架とマグダレーナ』(図336)である。ここでは正面性をもって表わされる神はもはや人間の姿をとらず、十字架の上で輝く光のみで表現されている。しかし十字架と両側の柱は、画面に対してほぼ左右相称、正面性をもって配されており、その意味は『セメレー』等と変わらない。この作品もやはり厚い塗りだが、山の緑と空の白は、人物が小さいことにも助けられて、『パルクと死の天使』より、さらに冷たく荒涼とした風景を描き出している。この冷たさによって、十字架とその光の、非人間的な性格が強調される。全体を支配する寒色に対して、褐色と赤がバランスを取るのだが、赤は十字架を伝わる血として、地面まで続いて、画面の凄惨な雰囲気を高める。右側を飛ぶ白い鳥たちの羽搏きも、空間を充たす静寂を印象づけるために配されている。マグダレーナの衣服も、厚塗りをナイフで切り刻んだような表面を示している。光輪にも血の赤が置かれている。この作品のための油彩習作が二点ほど残されているが(図337)、黄が多く用いられて、最終作ほど冷たい印象を与えていない。マグダレーナは両脚を伸ばしており、先に見た『ジオット』(図124→こちら)のポーズから出発したものであることがわかる。十字架の中央にはまだ光はなく、また両側の柱にも横木があって、十字をなしている。最終作ではこれが取り除かれて、中央の十字架を強調することになる。 十字架という形態が持つ、象徴的な表出力についてモローは、元来シャセリオーのサン・ロック教会の『インド人たちに洗礼を施す聖フランシスコ・ザビエル』(→こちらを参照)、また1840年の『オリーヴ園のキリスト』(図51→こちら)などに教えられたのであろう。『神秘の花』(図171→こちら)でも十字架の果たす役割りが大きかったが、以前にも何度かゴルゴタの丘の情景を描いており、『十字架とマグダレーナ』と同時期か少し以前にも、『キリストと二人の盗賊』(MGM.108)を描いている。これらの画面では十字架が非常に高く、また地面で人々が異変に騒ぐかのように、ざわめく姿が描かれている。しかし十字架を左右相称、正面性に配したのは『十字架とマグダレーナ』がはじめてで、十字架から人物を取り去ったのも勿論同じである。 |
 図336 《十字架とマグダレーナ》 MGM.208  図337 《十字架とマグダレーナ》 MGM.118 |
|||||||||||||||||||||||
| →[13]へ続く | ||||||||||||||||||||||||
| HOME>美術の話>ギュスターヴ・モロー研究序説 [12] |